第1週目(初週)朝ドラ『あんぱん』で印象的だったシーンは、第2話の吉田鋼太郎さん演じる朝田釜次が、パン屋の屋村(阿部サダヲ)に「1個10銭!? 高すぎる!」と驚く場面です。
「えっ、10銭ってそんなに高かったの?」
「というか、10銭って今で言うといくらなの…?」
そんな疑問を抱いた方も多いのではないでしょうか。
本記事では、この“あんぱん1個10銭”を出発点に、昭和初期から現代に至るまでの物価の移り変わりや、給料の推移から見るお金の感覚をわかりやすく解説していきます。
「物価って昔と今でどれくらい違うの?」
「昔の給料で何が買えたの?」
――そんな素朴な疑問を、“あんぱん”という身近な存在を通して一緒に見ていきましょう!

当時の物価や給料、さらには人々の生活感覚を映し出す大切な手がかり。数字の向こう側にある日本の暮らしの変遷を探っていくよ。
あんぱん10銭は今の「357円」!昭和初期の物価を現代換算
朝ドラ『あんぱん』第2話で、阿部サダヲさん演じる屋村が売っていたパンの値段が「1個10銭」と聞いて、「えっそんなに!?」と驚いた反応を見せた朝田釜次(吉田鋼太郎)。しかし、ピンとこなかった視聴者も多かったのではないでしょうか。
🏃♀️#きょうのあんぱん🖌
— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) March 31, 2025
嵩が食べさせてもらった、焼きたてのパン。
このパンを焼いてくれた人物とは…?
おいしそうなパンを初めて見たのぶの目は、キラキラ輝きます👀✨#永瀬ゆずな #木村優来 #阿部サダヲ#朝ドラあんぱん pic.twitter.com/gJKfIPWZHF

10銭=1円の10分の1ってことは…すごい安そうだけど?と思って、調べてみると…当時の1銭は、現代の6円〜8円くらいだったとか!
これは、当時の物価や賃金水準、そして消費者物価指数(CPI)からの換算などをもとにした概算値です。1銭が約6〜8円相当とされており、それが10枚であればこの金額になります。

10銭って、今で言えば駄菓子じゃなくて“ちょっとしたご褒美パン”って感じ?庶民のおやつにしては高級寄りだったかも。
ちなみに、昭和初期の物価の一例としてはこんな感じです。
| 品目 | 昭和2年(1927年)の価格 | 現在価値の目安 |
|---|---|---|
| あんぱん(1個) | 約10銭 | 約60〜80円 |
| 食パン(1斤) | 約14銭 | 約90〜110円 |
| うどん(屋台) | 約8銭 | 約50〜70円 |
| 銭湯入浴料 | 約5銭 | 約30〜50円 |
こうして見ると、10銭というのは「ちょっとした贅沢」に感じられる金額だったことが分かります。
さらに、当時の大卒初任給は約70円前後。つまり、10銭のあんぱんは月給の700分の1。今の初任給が25万円とすると、だいたい357円くらいの価値とも考えられます。

金額だけじゃなくて“給料に対する割合”で見るとリアルに感じるね。物の価値って、その時代の生活水準とセットで考えると面白い◎
昭和・戦後・バブル・令和…パンの値段はどう変わった?
昭和初期に10銭だったあんぱんは、その後どのように値上がりしていったのでしょうか?ここでは、時代ごとのあんぱんの価格推移をまとめて紹介します。
🏃♀️#きょうのあんぱん🖌
— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) April 4, 2025
朝田家に焼きたてのあんぱんを持ってきた草吉。
朝田家の人々は、ホカホカのあんぱんに生きる力をもらいました☺️✨#江口のりこ #吉田鋼太郎 #浅田美代子 #細田佳央太#永瀬ゆずな #木村優来 #吉川さくら #永谷咲笑 #阿部サダヲ#朝ドラあんぱん pic.twitter.com/9HAG2pLp9U

パンってずっと安いイメージあるけど、実はめっちゃ変わってきたみたい。時代によって原料価格も影響してるし、戦争や高度成長期も大きいよ!
| 年代 | あんぱんの価格(当時) | 現代の価値換算(目安) |
|---|---|---|
| 昭和初期(1930年) | 約3〜5銭 | 約30〜50円 |
| 戦後(1950年) | 約10〜12円 | 約90〜100円 |
| 高度成長期(1970年) | 約20〜60円 | 約100〜150円 |
| バブル期(1980〜90年) | 約100〜120円 | 約120〜140円 |
| 令和(現代) | 約120〜150円 | 約120〜150円(実質ほぼ同じ) |

物価って右肩上がりに見えるけど、実質価値では大きな変化がない時代も…。特に平成以降はパンの価格もほぼ横ばいで、デフレの影響が色濃く出てるね。
これは原材料価格や流通、技術の安定、そして日本全体の経済成長率の鈍化によるものといえます。
また、近年は材料費や人件費の高騰によってやや値上がり傾向にはありますが、それでもパン1個あたり120〜150円程度。なんと、約100年かけて“実質価格”はそこまで大きく変わっていないというのが面白いところです!

時代は変わっても、あんぱん1個に込められた「日常の小さな幸せ」は同じ。なんか、昔の人とつながってる気がするね♪
【図解】物価だけじゃない!給料の推移から見る“あんぱんの重み”
「当時の物価は安かった」という話はよく聞きますが、それだけではお金の“重み”は分かりません。
そこで注目したいのが、各時代の初任給(大卒)です。初任給で何個のあんぱんが買えたかを比べると、当時のお金の感覚がよりリアルに伝わってきます。

昔の人って、給料どのくらいで生活してたんだろ?初任給で買える“あんぱんの個数”を比べると、お金の感覚が見えてくるよ!
| 年代 | 初任給(大卒) | あんぱんの価格 | 月給で買えるあんぱんの数(目安) |
|---|---|---|---|
| 昭和2年(1927年) | 約70円 | 約0.1円(10銭) | 約700個 |
| 昭和30年(1955年) | 約11,000円 | 約10円 | 約1,100個 |
| 昭和45年(1970年) | 約39,900円 | 約25円 | 約1,596個 |
| 平成2年(1990年) | 約190,000円 | 約100円 | 約1,900個 |
| 令和(現在) | 約250,000円 | 約140円 | 約1,785個 |


あれ?今って、昔より“たくさん買える”ってわけでもない?ここでも日本経済の成長鈍化の影響が…!意外と昔の方が“コスパが良い”時代もあったんだね。
たとえば、昭和初期は月給70円でもあんぱんが700個も買えました。一方で、現代の初任給25万円で買えるのは約1,785個。
名目上の金額は大きく違っても、「給料で何がどれだけ買えるか」=購買力で見ると、昔と今でそこまで極端な差がないことが分かります。

数字じゃピンと来なかったけど、あんぱんが“何個買えるか”だと分かりやすい!パンって意外と日本経済を映す鏡かもね♪
【銭、厘、円の価値】10銭、1銭は現代のいくら?何が買えた?
今では聞きなれない「銭(せん)」や「厘(りん)」という単位。かつては日本で当たり前のように使われていたお金の単位です。

銭は1円の100分の1?明治〜昭和初期までは、“銭”や“厘”が日常的に使われてたようだけど、ちょっとピンとこないかも…。
- 1円 = 100銭
- 1銭 = 10厘
つまり、「10銭」は今でいう「0.1円(10分の1円)」に相当します。江戸時代の「文(もん)」に代わって、明治4年(1871年)の新貨条例から登場しました。

明治〜大正時代なら、1銭でお菓子や新聞も買えたよ!具体的に買えた物って何か見てみよう。
例えば――
「1銭」や「10銭」は、子どもでも持てるお金として、駄菓子屋や新聞売り場などで活躍していたんですね。
しかし、戦後の激しいインフレにより、銭や厘では買えるものがなくなってしまいました。1948年には補助通貨の発行が停止、1953年の通貨改正法(小額通貨整理法)によって「銭」「厘」は正式に廃止され、完全に姿を消しました。

今じゃ10銭玉とか幻の通貨。残ってるのは記念品かコレクターアイテム!でも、当時は“本物のお金”だったって、感慨深いね。
今でこそ1円玉が最小単位ですが、かつては「銭」や「厘」でも立派な日常のお金でした。だからこそ、朝ドラの時代背景を知るうえで、こうした通貨単位もとっても大事なヒントになるんです。
【朝ドラの見どころ】時代とともに変わる“物の価値”を楽しむ視点
今回、朝ドラ『あんぱん』の“10銭あんぱん”から始まった時代考察。でも実は、こうした「物の値段」や「通貨の価値」に注目することで、他の朝ドラや時代劇もぐっと面白く見えてくるんです。
🏃♀️ 明日です!#今田美桜 #北村匠海#朝ドラあんぱん
— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) March 30, 2025
📅3月31日(月)スタート🏃https://t.co/0O3u41JR1X pic.twitter.com/xPBrKJzHLp

朝ドラでまた物の値段出てきたら、今いくらか気になっちゃうね。こうやって物価や給料を比べると、ドラマがもっと面白くなるよ!
たとえば――
その金額だけを見ると「安い!」と驚いてしまいますが、実際は当時の給料や生活水準とセットで考えることが重要。
現代の感覚に落とし込んで「今だといくら相当かな?」と想像することで、当時の人々の暮らしや価値観がぐっとリアルに感じられるようになります。

SNSでも「この時代って、今でいうと○○円!」って投稿、けっこう見るよね。ちょっとした“知識の共有”で、見てるドラマが一気に盛り上がる感じ好きだな~。

「この時代ならあのセリフ、○○円ってことか!」とコメントすれば、フォロワーとの話題も広がるかも。この記事で知ったことがあれば、共有してみてね。
今後も朝ドラや時代劇で「当時の値段」や「通貨単位」が登場したときには、ぜひ“物価と給料の関係”をチェックしてみてください。
\物価と貨幣価値算出方法は様々!類似記事はこちら/
≫【嘘解きレトリック】昭和初期の50円!現代に換算するといくらかはこちら
まとめ:あんぱん10銭から見える、100年分の日本の暮らし
ドラマでの「あんぱん10銭」から、私たちは100年にわたる日本の暮らしの変化を垣間見ることができました。
あんぱんの値段はもちろん、給料、物価、通貨単位…それぞれの数字には、その時代に生きた人々の価値観や生活のリアルが詰まっています。

こうやって見てくると、数字の向こうに“人の暮らし”が見える気がする!「物の値段」って、単なる数字じゃなくて“時代を映す鏡”なんだね◎
給料・物価・そしてあんぱん。身近なものを通して知る「日本経済100年」は、誰でも楽しめる時代考察です。
朝ドラ『あんぱん』をきっかけに、今後も物価の変化に注目しながら、ドラマを深掘りする記事を随時更新予定です!気になった方は、ぜひブックマークしておいてくださいね♪

ドラマやこの記事の感想があれば、コメント欄で教えてね。ここってちょっと違うんじゃない?って指摘も大歓迎です。
- 3週目:嵩が漫画賞で賞金10円をもらった!
≫賞金10円って今だといくら?昭和10円で買えるもの、物価解説はこちら - 3週目:朝田パンの『あんぱん』は4銭!
≫あんぱん4銭はいくら?昭和10年の物価、今だと何円になるかはこちら - 2週目:最初に売り出した朝田パンの『あんぱん』は3銭!
≫1銭はいくら?あんぱん3銭に見る、昭和初期と今現在の物価感覚の比較はこちら
≫『あんぱん』週のネタバレまとめ!週末振り返り&次週の展開予想はこちら
参考文献・出典:昭和40年の1万円を、今のお金に換算するとどの位になりますか?(日本銀行)、昭和30年年次経済報告 都市生活者の状況(内閣府経済企画庁)、大卒初任給(年次統計)、 政府統計ポータルe-Stat「小売物価統計調査」、消費者物価指数(総務省統計局)、厚生労働省「賃金構造基本統計調査」などの一次資料、および『値段史年表 明治・大正・昭和』、昭和毎日新聞資料、あんぱん・ジャムぱんの値段の推移(戦後昭和史)、1銭の価値は現在だといくら?(BUYSELL)、日本のインフレの歴史(ポラスグループ)


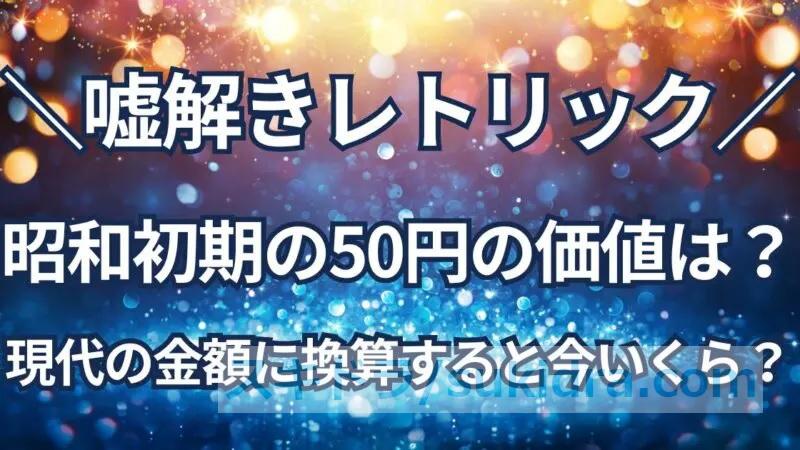

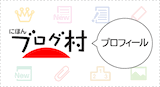

コメント