朝ドラ『あんぱん』第10週「生きろ」は、涙なしでは見られない激動の展開へ。草吉が語る壮絶な戦争体験、次々と届く召集令状、そして嵩の出征――。
登美子の「死んじゃだめ!」という叫びが視聴者の胸を打ち、戦時下で“生き抜くこと”の大切さを静かに訴えかけます。
本記事では、ネタバレを含むドラマのあらすじと共に、やなせたかし氏の実話とドラマの重なりを丁寧に解説。のぶ・嵩・草吉…それぞれの“迷いと希望”を通じて、第10週の深いテーマを読み解きます。
≫【あんぱん】9週目『絶望の隣は希望』あらすじ、ネタバレ感想!はこちら
【ネタバレ】第10週「生きろ」あらすじ
乾パンの注文を断固拒否した草吉(ヤムおんちゃん)が釜次に語ったのは、第一次世界大戦の壮絶な塹壕戦(ざんごうせん)での体験。餓死寸前の戦場で乾パンだけが命をつなぐ唯一の食料だったこと、そして仲間の死の記憶が、今も彼の中で癒えていない傷として残っていたのです。

乾パンは辛い体験を思い出させるものだったんだね。釜じいが「もう、これ以上あいつを苦しめたらいかんがじゃ」と言った意味が分かったよ…。
昭和16年(1941年)12月8日。日本軍がハワイの真珠湾を攻撃し、太平洋戦争へ突入。戦局が悪化する中、若者たちは“戦場”という運命に次々と飲み込まれていきます。

“お国のために”って言葉が、こんなにも重いなんて…。健ちゃんを見送る夜に一緒に食べたカレーライス…忘れられない…。今度は笑いながら食べたいね。
🏃♀️#きょうのあんぱん🖌
— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) June 3, 2025
健太郎のもとに赤紙が来ました。
明るく振る舞う健太郎でしたが…
「…また会えたら良かね」
「会えるに決まってるだろ!…生きて、また会おう」
🔻二人はある約束をし…https://t.co/sc4pgOgHON#北村匠海 #高橋文哉#朝ドラあんぱん pic.twitter.com/UOwSBkmzEe
高知では、航海を中止して帰宅した次郎とのぶが束の間の時間を共に過ごしますが、次の航海では兵隊や軍需物資を運ぶ任務が待っていると聞かされ、のぶは言葉を失います。
そして――。嵩の出征の日。人々が「立派にご奉公を」と声をかけるなか、母・登美子は叫びます。
非国民と糾弾されそうになる中、のぶも登美子の想いに同調し、「生きて帰ってきて」と叫ぶ――。

登美子さんの叫び、戦時中にあんな言葉よく言えたよ…すごい勇気!憲兵が駆けつけて連行されそうになる中、本当の母の叫びを聞いたよね。
教師として“立派な兵隊になれ”と教えていたのぶが、揺れに揺れる週。それでも、自らの本音と生徒への“ほんとうの授業”のヒントを見出し始める姿が、静かに描かれていきます。
【考察①】草吉が語った「乾パンと戦争」第一次世界大戦の塹壕体験
軍隊へ提供する乾パン作りを頑なに拒否していたヤムおんちゃん。彼の過去に何があったのか?10週ではその辛い過去が明らかとなっていきます。
「So hungry to death」──餓死寸前の兵士たち
ヤムおんちゃんこと草吉の秘密が明かされる衝撃のエピソード。それは、かつて彼が第一次世界大戦にイギリス軍の義勇兵として参加し、地獄のような塹壕戦(歩兵が敵弾を避けるために掘った穴に隠れ、そこから攻撃を繰り出す戦術)を経験したという過去。
あまりにもリアルな語りに、視聴者は戦争の過酷さと“食”の重みに息を呑みました。

“死ぬほどお腹が減っている”と乾パンをかじりながら笑っていた隣の仲間が…次の瞬間、頭が吹き飛んでたって…トラウマだよ…。
塹壕の中で唯一の命綱だったのが乾パンだった。だからこそ、草吉にとって“乾パン”は兵士の死と結びついた記憶。パン職人として誇りを持つ彼が、それだけは作りたくなかった理由が、痛いほど胸に迫ります。
🏃♀️#きょうのあんぱん🖌
— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) June 1, 2025
草吉には、欧州大戦をイギリス軍の日本人義勇兵として戦った過去がありました。
空腹で苦しむ極限状態の中、倒れて動けない仲間の懐から奪って食べた乾パンは、今でも草吉を苦しめるものでした。#阿部サダヲ #吉田鋼太郎#朝ドラあんぱん pic.twitter.com/jNa18IqqlI

実際の戦争でも、死因で最も多いのは“飢え”なんだって。パン作り=命をつなぐこと…ヤムおんちゃんの過去を知ると、見方が変わるよね。
ドラマの描写とやなせ氏の思想との共鳴
草吉の言葉に強く共鳴するのが、モデルとなったやなせたかし氏の“戦後のメッセージ”です。
著書『ぼくは戦争は大きらい』の中でも、「正義よりもまず食べ物が必要だった」と語るやなせ氏。彼は戦地での空腹と過酷な日々を何よりも深く記憶しており、「食べる=生きる」というシンプルで普遍的な価値観を、後に“アンパンマン”という作品に込めました。

食べること=生きること。パンって、命そのものだったんだね…。やなせたかし先生の著書は読みやすいけど、とても考えさせられる内容だったよ。
そして、草吉の退場は、まるで“命のバトン”を朝田家の人々に託したかのよう。のぶもまた、「教師」として“夢”を語れる授業へと一歩踏み出そうとしていました。
【考察②】嵩の出征と母の叫び:「死んじゃだめ!」に託された願い
今まで自由奔放に生きているかのように見えていた嵩の母・登美子。しかし、嵩の出征の日、非国民として連行されそうになりながらも嵩に叫んだ言葉は、当時、戦地へ赴く息子を見送る母の本音だったと言えるのではないでしょうか。
母・登美子の言葉がもたらした波紋
「嵩! 死んじゃだめよ!」――高知の町を揺るがすほどの叫び声が響いたその瞬間、空気が凍りました。出征を控えた嵩を見送る商店街の人々が「お国のため、立派にご奉公を!」と声を上げる中、は涙ながらに息子へ“生きて帰れ”と叫びました。

えっ…登美子さん…!戦時中にこんなこと言うなんて、命がけ…!でもきっと、登美子さんの叫びは、当時の息子を見送る母の心の叫びだったよね。
🏃♀️#きょうのあんぱん🖌
— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) June 5, 2025
嵩の出征当日。
そこには、いるはずのない登美子の姿が…
「逃げ回っていいから。卑きょうだと思われてもいい。何をしてもいいから…生きて、生きて帰ってきなさい!」#北村匠海 #松嶋菜々子#朝ドラあんぱん 見逃し配信中📱https://t.co/pNI6JKR4O0 pic.twitter.com/7QZD3SQCjF
のぶもその声に心を動かされます。教師として生徒に「立派な兵隊に」と教えてきた自分に疑問を抱き始めていた矢先でした。

朝ドラとしては“戦争”に対し、踏み込んだ声!“ご奉公”より“生きて”って…建前と本音がぶつかりあった瞬間だったね。
“お国のため”という正義の裏に隠された“母の願い”が、涙と共に描かれました。
🏃♀️#きょうのあんぱん🖌
— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) June 6, 2025
登美子をかばうように前へ出たのぶ。
「嵩、必ずもんてき!お母さんのために、生きてもんてき!」
🔻その言葉に嵩は…https://t.co/tYOSK2MfBS#今田美桜 #北村匠海#朝ドラあんぱん pic.twitter.com/IxLKHSi33E
「非国民」と呼ばれても、伝えたかったこと
嵩の敬礼とともに、騒動はなんとか収束しましたが、この一連のシーンが投げかけたのは、「命よりも国家の名誉が大事なのか?」という問いでした。
登美子ものぶも、戦時下では“非国民”として糾弾されてもおかしくない言動をしています。しかし、それは家族の命を守りたいという純粋な願いから生まれたものでした。

嵩の敬礼も…泣けた…母と先生を守るために“大人”になった感じ…!そして、登美子さんはやっぱり、嵩の“母親”だったんだね…。
嵩の「かばう」行動もまた、大人としての第一歩。命を軽んじる空気の中で、家族への“愛”を選んだこのシーンは、まさに今の時代にも響くメッセージを内包していました。
【実話検証】やなせたかし氏の実話と重なる出征の記憶
やなせたかし氏の著書『ぼくは戦争は大きらい』では、他のやなせ作品とは全く違う“やなせ氏の実際い体験した戦時中のこと”が書かれています。
やなせ氏の軍歴:小倉の西部第73部隊に配属
ドラマで嵩が配属されたのは「福岡・小倉の連隊」。これは実在のやなせたかし氏の軍歴と一致しています。
やなせ氏は昭和15年春、やなせ氏の元に召集令状が届きました。高知にて徴兵検査を受け、視力が悪いながらも第一乙種で合格。当初は地元・高知の歩兵連隊への配属かと思われましたが、担当将校から「お前は係累がいないからどこにでも行けるな」と言われ、小倉の西部第73部隊に転属されます。

“係累(面倒を見ないといけない家族)がいない”って理由で転属って…今じゃ考えられない。でも、これが功を奏したとやなせ氏。
小倉での任務は「馬部隊」。朝は厩舎の掃除から始まり、馬の体を洗い、エサをやり…兵舎の生活は、まさに“馬中心”。さらに戦車迎撃訓練では、爆弾を竹の先につけて突撃するという非現実的な練習も行われていたと記されています。
旧式の日本軍、そして“理不尽な日々”を笑い飛ばす強さ
やなせ氏は「大八車を戦車に見立てて、ヤーッと突撃させられる訓練」に対し、「こんなことで本物の戦車に勝てるわけがない」と冷静に突っ込んでいます。
また、使用する銃も三八式歩兵銃で、一発ずつ弾を込める旧式なもの。アメリカ軍がすでに連発式を導入していたことに、やなせ氏は日本軍の“時代遅れ”を痛感していたと語っています。

“寒夜に霜が降りるごとく引き金を引け”と教えられたって…相手は連発銃を使っているのに、こっちは一発ずつ弾を込めている時点で終わってるよ~。
ただ、やなせ氏はそんな理不尽な軍隊生活にも「要領を覚えれば生き抜ける」と語り、少しずつ順応していきました。現実から目を逸らさず、著書ではあえてユーモアを交えて語れるその強さが、のちのアンパンマンの哲学「正義よりも食べ物」「飢えを救うことが正義」へと繋がっていきます。

もちろん、体験した当時はそんな余裕なかったのかもしれないけど…本では小学生にも読めるよう、分かりやすくしてくれて…感謝しかないよね。
\戦争を知らない私たちへ、子どもにもおすすめ/
【時代背景】のぶと次郎の未来「生きるために夢を見る」日常を守る希望
登美子の絶叫、嵩の出征を間近に見たのぶの胸には、“お国のため”と子どもに教えつつも、疑心が芽生えは始めます。
戦争の只中で語られた、のぶの“本当の夢”
のぶが次郎と語った夢──
これは“愛国の鑑”と讃えられたのぶの、教師としての、そして一人の女性としての本音でした。
けれど、「僕は、この戦争に勝てるとは思わん」と言う次郎に「そんなこと思うてはいけません!」と言い、「生きて帰ってきて」とは言えず…建前としての「立派なご奉公を」を口にしてしまったのぶ。戦時下における“理想と現実”の隔たりが、のぶを静かに苦しめていきます。

本音では“生きて”って思ってても…言えないのが戦争なんだよね…。そう考えると、やなせ氏が言うように、登美子さんは時代の先を行く女性だったんだなぁ…。
🏃♀️#きょうのあんぱん🖌
— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) June 4, 2025
戦争が終わったら、のぶがしたいことは…
「生徒らあに楽しい授業をしたい」
「それから…次郎さんと一緒に船に乗って、色んな国に行ってみたい」
それを聞いて嬉しそうにほほ笑む次郎です#今田美桜 #中島歩 #朝ドラあんぱん 見逃し配信中📱https://t.co/MvcnUPtSot pic.twitter.com/MU2EVWAB0I
命を守ることこそが教育!草吉と教師・のぶの共通点
草吉が語った塹壕の記憶――飢え、死、仲間の最期。そしてそこで唯一食べられた乾パン。命を繋ぐ“食べ物”の大切さは、草吉が朝田パンに込めた魂そのものでした。
一方でのぶもまた、教育者としての苦悩を抱えています。「子どもに夢を語れない」「勝てるとは思えない戦争を信じろと言わなければならない」──この苦しみは、草吉が抱えた“乾パンを作れない理由”と通じるものがありました。

教師として、母として、“命を守る”ってどういうことかを問われた週。今も世界では争いが絶えないけど、戦時中を生きた人の声に学んでほしいと願っちゃうね。
“戦うこと”ではなく“生き抜くこと”を選ぶ人々を描いた第10週。嵩・草吉・のぶ・登美子――それぞれの立場で「命」を叫んだ週だったと言えるでしょう。
🏃♀️#来週のあんぱんは?🖌
— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) June 1, 2025
第10週「生きろ」予告動画🎥
草吉の過去を釜次から聞いたのぶは…。激化する戦争。
そのころ、東京の製薬会社に勤めている嵩は…
🔻あらすじはコチラ📖https://t.co/WbaccjyfwT#今田美桜 #北村匠海#朝ドラあんぱん 見逃し配信中📱https://t.co/bztmNtJZbt pic.twitter.com/NeNSiUIzzs
\読書感想文にもおすすめ!子どもに読ませたい本/
まとめ:“死んじゃだめ”が響く週…命を守ることの尊さを描く
第10週「生きろ」は、まさに“命をどう守るか”が問われた週でした。草吉が語った地獄のような戦場体験、健太郎・嵩・次郎の出征、そして「非国民」と言われながらも“生きて帰れ”と叫ぶ登美子――。戦時下で生きる人々の葛藤と、日々の営みの尊さが丁寧に描かれました。
のぶもまた、「教師として建前を教えるのか」「一人の人間として夢を語れるのか」の間で揺れ続けます。

“正義”じゃなくて“生きる”ことが一番大事。登美子さんの叫びが、そのすべてを代弁してた気がする…!
\今までの復習と予習はこちら/
≫『あんぱん』今週のネタバレ全まとめ!週末振り返り&来週の展開予想【朝ドラ2025】
≫【あんぱん】11週目『軍隊は大嫌い、だけど』あらすじ、ネタバレ感想!はこちら







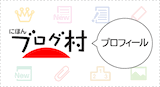

コメント