朝ドラ『あんぱん』第7週『海と涙と私と』第35回では、のぶがついに母校・御免与尋常小学校の先生に!女子師範学校での努力を経て、夢だった“教壇に立つ日”が描かれ、多くの視聴者の心を打ちました。
でもふと疑問に思いませんか?「当時って、どうやって先生になれたの?」「母校に戻って教えるってよくあることだったの?」――と。
本記事では、のぶの就職エピソードをネタバレ込みで振り返りながら、昭和初期の教員免許制度・採用ルート・女子師範学校の仕組み、実在モデル・小松暢さんの通った学校(旧制高等女学校)と女子師範学校との違いについても解説します。

ドラマをもっと深く味わいたい方へ、時代背景をひもとく一助になれば幸いです。7週目のネタバレを含むので、ご注意ください。
【第35話ネタバレあらすじ】のぶが小学校の先生に!
ついに、のぶの夢が叶う瞬間がやってきました。女子師範学校の寮で掃除中だったのぶのもとに、黒井先生が封筒を手渡します。
これは偶然ではなく、のぶの努力と人柄、そして黒井先生の推薦があってこそ。志を同じくして学んできた同期の小川うさ子は、師範学校に残って助教に。2人はそれぞれの道へと進みます。
そして。昭和14年(1939年)4月、制服姿で初めて教室に立ったのぶが、笑顔で子どもたちにあいさつする場面は、まさに“夢の実現”を象徴する感動的なシーンでした。

夢だった“母校の先生”に…感無量の瞬間!今までは“先生”って呼んでいたけど、今度は“先生”と呼ばれる側に…!
🏃♀️#きょうのあんぱん🖌
— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) April 15, 2025
家族と町の子どもたちにラジオ体操を教えるのぶ。
これまでに味わったことのない楽しさと爽快感…✨
「嵩、うち、見つけたかもしれん……」
🔻のぶが見つけたものとは?https://t.co/WUIieKExtK#今田美桜 #北村匠海 #中沢元紀#朝ドラあんぱん pic.twitter.com/lvBoVgqMrQ
【時代背景】昭和初期の小学校教員になるには?女子師範学校とは
今では教員になるためには“教員採用試験”がありますが、昭和13年当時はどのようにして教員になれたのでしょうか。ここで教員になる方法を見ていきましょう。
女子師範学校の役割とは?
のぶが通っていた女子師範学校は、今でいう“教員養成大学”のような存在。中学校(当時の高等女学校など)を卒業した女性たちが、さらに専門的に「教育」を学ぶための公的機関です。

ドラマでも“あなたたちの学費は官費(国の出す費用)でまかなわれている”って黒井先生が言っていたね。学費免除=国の役に立つ人材を育てるって意味かぁ…。
授業では国語や算術はもちろん、教育心理や児童指導、裁縫・唱歌など、初等教育に必要な知識と技術を徹底的に学びます。さらに、授業だけでは終わりません。実際の小学校での教育実習もあり、先生になる準備を段階的に積んでいくのです。
また、当時の女子師範学校は規律が非常に厳しく、全寮制が基本。門限・恋愛禁止・礼儀作法の徹底など、“先生になる自覚”を養うための生活指導もバッチリでした。
≫女子師範学校の寮はどんなところ?規則や1日のスケジュール、門限・恋愛禁止ルールについて
卒業生には教員任用の義務が課され、ほぼ例外なく教師となる道が開かれていました。つまり、のぶのように「女子師範学校に通えば先生になれる」は、当時としてはごく当たり前の進路だったのです。
教員採用の流れは?今とどう違う?
現代の教員採用といえば、“筆記試験・面接・集団討論”などの関門をくぐり抜ける、ガチガチの就職競争ですよね。ところが、昭和初期の教員採用はちょっと違いました。
とくに多かったのが、“母校への赴任”。のぶのように「かつて通った小学校に戻って教える」というパターンは、教員不足が深刻だった地方ではとても重宝されました。

今みたいに“筆記+面接”で点数勝負じゃなかったんだね。逆に“信頼”や“縁”が命…なんか人情の世界って感じ!
“先生の卵”を地域全体で育て、見守り、受け入れる――そんな温かみのある教育文化が、昭和初期の地方にはあったのです。
【実話検証】実在モデル・小松暢は旧制高等女学校出身!女子師範学校との違い
朝ドラ『あんぱん』で、のぶが進学した「女子師範学校」は教員養成のための専門校として描かれていますが――実在モデルとされる小松暢さん(やなせたかし氏の妻)は、女子師範学校ではなく「旧制高等女学校」出身です。

実際の暢さんは、大阪で旧制阿部野高等女学校(現:大阪府立阿倍野高等学校)を卒業。8女子師範学校ではないけど、何が違うんだろう…?
小松暢さんはどんな進路を歩んだ?教員ではなかった理由とは
小松暢さんは、大阪の旧制・阿倍野高等女学校を卒業後、日本郵船に就職。その後、戦後は高知新聞社で編集記者として活躍しました。
教職の記録は残っておらず、のぶのように師範学校から小学校教員になる道は歩んでいませんでした。
これは暢さん自身が「女子の教養」を身につける目的で高等女学校に進んだためであり、職業としての教員養成ルートとは異なっていたのです。

“女学校卒”って今で言うと短大+教養女子大みたいな立ち位置かも。だから、“のぶ=暢さん”の完全一致ではなく、あくまで“モデル”なんだね◎
女子師範学校と高等女学校の違いを比べてみよう!
どちらも女性のための教育機関ですが、目的も卒業後の進路も大きく異なります。
| 比較項目 | 女子師範学校 | 高等女学校9 |
|---|---|---|
| 設立目的 | 教員養成のための専門校 | 一般女子の教養教育 |
| 修業年限 | 4年 | 4〜5年(学校により異なる) |
| 卒業後の進路 | 小学校教員(原則) | 結婚、企業就職など |
| 教員免許の取得 | 卒業と同時に可能 | 不可(別途試験が必要) |
師範学校=教師を目指す女性のための“職業専門教育”。高等女学校=結婚・教養・社会進出を目指す“女子の花嫁修業”的存在。この違いを踏まえると、のぶと暢さんの進路差も自然に理解できます。
のぶの進路はフィクション?それとも“当時のリアル”?
ドラマ『あんぱん』で描かれたのぶのルートは、「女子師範学校で学び、母校に配属されて教師になる」というもの。これは実話そのものではないものの、昭和初期のリアルに即した王道パターンでした。
- 地元出身者が“恩師の推薦”で母校に戻る
- 就職試験はなく、成績+人柄で採用
- 教員不足を補う即戦力として重宝された

今でいうと“教育大卒の地元教員枠”みたいな感覚かも!制度+人情で成り立ってた時代だね◎
だからこそ、視聴者にも「こんな道、あったんだ」と自然に受け止められるストーリーとして成立しているのです。
まとめ:のぶが“小学校の先生”になったのは、女子師範学校卒業後のリアル
女子師範学校を卒業し、地元の母校に教員として戻る――のぶの就職ルートは、昭和初期の教育制度に即した自然な展開でした。
現代のように“競争型”の採用試験ではなく、「地元」「成績」「人柄」「推薦」などが重要視された時代。そこには、“制度×人間関係”で成り立つ、少しあたたかな就職文化がありました。
のぶが教壇に立つまでの道のりを知ることで、ドラマの描写に込められた「夢の重み」「社会のしくみ」も、より深く感じられるはずです。

知らないと見逃しちゃうリアリティ、たくさん詰まってたんだね!“のぶの先生デビュー”が、ますます尊く見えてきたんじゃないかな♪
- あまり出てこないけど、のぶが入っていた寮はマジで厳しかった…!
✅ 女子師範学校の寮はどんなところ?規則や1日のスケジュール、ルールを解説 - 黒井雪子先生って実際にいたの?モデルは誰で、どんな人?
✅ 黒井雪子先生のモデルは誰?本当にいたの?昭和の教師像、教員の採用制度とは? - 蘭子と豪の結婚の約束はどうなった?淡い恋の結末とは…?
✅ 【あんぱんネタバレ】豪は戦死!?蘭子との結婚の約束、恋の結末とは?
参考文献、資料:
- 第四節 教員及び教員養成(文部科学省) ↩︎
- 学校系統図(文部科学省) ↩︎
- 第一節 初等教育(文部科学省) ↩︎
- japanese-childhood(sites.manchester.ac.uk) ↩︎
- 教員の資格・待遇(文部科学省) ↩︎
- 教育職員免許状(Wikipedia) ↩︎
- 代用教員(Wikipedia) ↩︎
- 小松暢(Wikipedia) ↩︎
- 高等女学校(Wikipedia) ↩︎



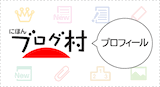

当サイトでは、話題の好きなドラマ情報をお届けします。
原作(小説・漫画・アニメ)のあらすじ・ネタバレ感想、ドラマのあらすじ・ネタバレ感想、原作との違い、原作書籍や配信先を紹介します。
推理小説好きなので、ミステリー要素がある作品が多くなるかも?気になる作品をピックアップしていきます。
他にもタイドラマのサイトを運営しているので、興味のある方は下記のサイトマークから覗いてみてください♡