明治初期(明治10年=1877年頃〜明治13年=1880年頃)を舞台にした朝ドラ『ばけばけ』では、舶来ウサギが高騰する「ウサギバブル」が登場します。
主人公トキの父・司之介が「数週間で200円を儲けた」と喜ぶシーンに、視聴者の多くが「200円って当時どれくらい?」「現代ならいくらの価値?」と気になったはず。
本記事では、1円・5円・200円・600円の現代換算をわかりやすく解説し、さらに実際に起こった「ウサギバブル」の史実も紹介します。当時の生活費や庶民の収入と比べながら、明治初期の“お金のリアル”を一緒にのぞいてみましょう!
明治初期(10年~13年)200円はいくら?⇒年収の数倍に匹敵!
朝ドラ『ばけばけ』のワンシーンでは、主人公の父が「ウサギで数週間のうちに200円のもうけを出した」と語られています。一見すると「200円」という額は小さく思えますが、明治初期(1877〜1880年頃)においては、庶民にとって想像もつかないほどの大金でした。

200円って、当時どれくらいの価値があったの?

調べてみるとね、庶民の年収が数十円〜せいぜい百円台だった時代。200円は庶民が何年も働いてようやく貯められる金額なんだよ。
当時の一般労働者の月収はわずか1〜3円程度、巡査や小学校教師でも月給8〜9円前後でした。つまり200円=年収の数倍から十倍以上という破格の数字。現代に置き換えると数百万円〜数千万円規模のインパクトがあります。
わずか数週間で200円を稼いだ主人公の父は、今で言えば「一気に高級車が買えるような儲け」を手にした感覚だったでしょう。
明治初期の1円・5円・600円の価値を現代換算
過去の貨幣価値については、一概に何円と単純計算はできません。例えば、明治時代の1円は現在いくらか。という問いに対しては、下記のレファレンス事例があります。
質問:明治時代の1円は現在いくらか。単純な答えが欲しい。回答
回答:「いくら」と数字にはできない。下記の3通りの考え方で調査。
・企業物価指数で考えると(②参照)、
明治34年の1円は令和4年の1832円、明治45年の1円は令和4年の1330円の価値がある。
・物の価格(白米中級品)で考えると(④⑥参照)
明治26年の1円は令和3年の約6618円、明治45年の1円は令和3年の約2569円の価値がある。
・給与(警察官の初任給)から考えると(⑦⑧⑨参照)、
明治19年の1円は令和5年の2万~4万の価値がある。

なるほど…。単純にいくらとは言えないわけか…。

それを踏まえて、以下のように考えたよ。
1円の価値
明治初期の1円は、現代ではおよそ2万〜3万円前後に相当するとされています。

えっ、あんパン100個!? 1円でパーティーできちゃう!というか、あんぱんって明治にあったんだ?

あんぱんは銀座木村家本店が明治7年に発売したのが最初。さらに警察官や教師の初任給が月8〜9円だったから、1円でも大切な給料の1/10なんだよ。
5円の価値
5円は、庶民の月収に匹敵するほどの大金です。
現代換算では10万〜15万円に相当します。劇中で「ウサギ1羽=5円」という取引が登場しますが、それは庶民にとって気軽に手が出せる額ではなかったことがわかります。

ウサギ1羽で月給並みって…!高級ブランドバッグ並みの買い物だね
200円の価値
200円は、すでに「夢のような大金」です。
当時の記録では、アメリカ製の自転車が200〜250円しました。つまり200円あれば「自転車=現代なら車を買える」ほどの財力でした。
現代価値では数百万円〜600万円規模と考えられます。200円を儲けた主人公の父は、数日にして庶民の何年分もの稼ぎを手にしたのです。

やっぱり“バブルの匂い”がするね…。そりゃ夢中になるよ!
600円の価値
ウサギの相場が過熱したピークには、600円という値がついたことも記録されています。
当時の高官(右大臣クラス)の月給が600円前後2だったため、これはまさに国家の要職者の月収と同等の金額。現代に直せば数千万円規模であり、ウサギ1羽が「家や土地と同じ価値」で売買されたのです。

ウサギ1羽が大臣の給料って、バブルすぎるでしょ!?

そう。当時の人も“狂乱”って呼んでたぐらいだし、今じゃ考えられないよね。
明治初期の「ウサギバブル」とは?
平均寿命7~8年とも言われるウサギが、なぜ投機対象となったのか?本当にあった、ウサギバブルの背景を見ていきましょう。
ブームの発端
明治初期、東京を中心に突如として広まったのが舶来ウサギのブームです。ヨーロッパから入ってきた耳の長いウサギや珍しい毛並みのウサギは、当時の人々にとってとても珍しく、富裕層の間でステータスシンボルのペットとして人気を集めました。

確かに可愛いけど…どうしてウサギがそんなに人気になったの?

見た目の珍しさだけじゃなくてね、“毛皮や肉が軍需品に役立つかもしれない”って期待もあったんだよ。
こうした背景から、ウサギは単なる愛玩動物を超えて「飼えば儲かる」投資対象として注目されるようになりました。
投機熱のピーク
ウサギ人気は一気に過熱し、街の待合茶屋では「兎会(うさぎかい)」と呼ばれる集まりが開かれました。そこではウサギを持ち寄って品評したり、オークション形式で売買したりする競売が日常的に行われたのです。
中でも価値が跳ね上がったのが、更紗模様のウサギ(白地に黒い斑点がある珍しい毛色)。この種ウサギは1羽で200円から600円という驚くべき価格で取引されました。

200円〜600円って、当時なら家や土地レベルの大金だよね…!

しかも“種付け料”として1回2〜3円を取るビジネスも流行って、まさに投機熱に火がついたんだ。
人々はこぞってウサギを飼育し、「増やせば一財産築ける!」と夢を託しました。
規制とバブル崩壊
しかし、ブームの熱狂はやがて社会問題化します。価格の高騰で破産する者や、偽装したウサギを売る詐欺が横行したため、東京府は明治6年(1873年)に「兎会」禁止令を出しました。
さらに、翌年には兎税制度を導入。
この厳しい規制によって投機熱は一気に冷め、ウサギ相場は大暴落。人々は税金を払えず、飼育放棄や処分が相次ぎ、ブームは急速に終焉を迎えました。

えっ…夢のウサギが、一気に“負債のもと”に変わったんだね。

そう。当時の新聞にも“川にウサギを捨てる人がいる”なんて記事が出たくらいだよ。
こうして、ウサギバブルは数年で崩壊。人々の熱狂と失望は、まさに近代日本最初期の“バブル経済”の縮図でした。
なぜ「ウサギバブル」が朝ドラ『ばけばけ』に描かれたのか
朝ドラ『ばけばけ』では、主人公の父がウサギ相場に乗って200円の大金を儲けるものの、ブームの崩壊で借金を背負う姿が描かれます。
これは単なる娯楽的エピソードではなく、史実のウサギバブルを下敷きにしています。庶民にとって一攫千金の夢を見られるチャンスだった一方、熱狂に呑まれた多くの人が破産し、絶望を味わったのです。

つまり、ドラマでは“庶民の夢と破滅”を象徴してるんだね。

うん。『ばけばけ』は人物の生活感を通して“時代のリアル”を描く作品だから、バブルの狂乱はピッタリなんだよ。
このエピソードを通じて、『ばけばけ』は「儲け話に飛びつく人間の欲」と「夢の崩壊」という普遍的なテーマを浮かび上がらせています。
明治10年前後の貨幣価値とウサギバブル:まとめ
明治初期(明治10年前後)の1円=現代で数万円に相当し、庶民の月収は数円から十数円程度。そんな中で「200円を稼ぐ」というのは、今で言えば数百万円〜数千万円の大儲けに匹敵する出来事でした。
そして、史実として存在した「ウサギバブル」は、人々がウサギに熱狂して200〜600円で売買するほど相場が膨れ上がり、やがて規制と暴落で終焉を迎えました。
朝ドラ『ばけばけ』で描かれたのは、まさに「庶民の夢と破滅」を象徴する史実。物価やお金の感覚を知ることで、ドラマのシーンがさらにリアルに感じられるのではないでしょうか。

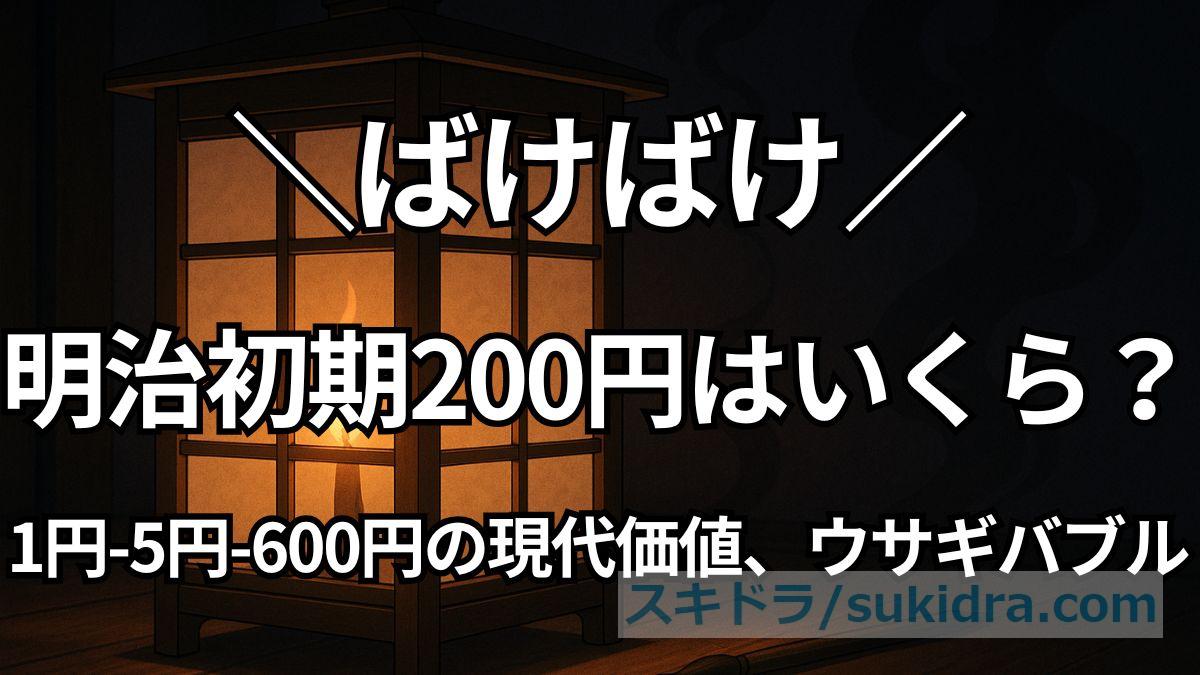
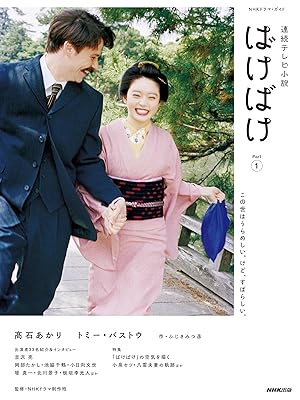


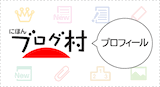

当サイトでは、話題の好きなドラマ情報をお届けします。
原作(小説・漫画・アニメ)のあらすじ・ネタバレ感想、ドラマのあらすじ・ネタバレ感想、原作との違い、原作書籍や配信先を紹介します。
推理小説好きなので、ミステリー要素がある作品が多くなるかも?気になる作品をピックアップしていきます。
他にもタイドラマのサイトを運営しているので、興味のある方は下記のサイトマークから覗いてみてください♡