第6週「ドコ、モ、ジゴク。」(11月3日〜):視聴率14.9%
松江中学校での授業が始まったヘブンは、堂々と英語を話し、生徒たちの心をつかみます。通訳の錦織が「先生についていけば、誰でも英語を聞き取れるようになる」と励ますと、生徒たちは一斉に「頑張ります!」と声をそろえ、教室は明るい希望に包まれました。
しかし旅館に戻ると、ウメがまだ医者に診せてもらっていないことを知り激昂。「オヌシ、ジゴク!」と叫び、旅館主・平太を叱責。ついに旅館を出る決意を固めます。
錦織はヘブンのために新しい住まいを探す一方で、身の回りの世話をする「女中」を雇う話を進めることに。ところが、当時“外国人に仕える女中”は「ラシャメン(洋妾)」と蔑まれており、誰も名乗り出ませんでした。そんな中、遊郭を出たいと願うなみが志願するも、百姓の娘だと知ったヘブンは難色を示します。
錦織は次にトキを訪ね、「ヘブン先生は士族の娘がいいと言っている。月二十円の給金だ」と持ちかけます。しかし、誇り高いトキは「馬鹿にせんでごしなさい!」と激怒。家に戻った後もその言葉が頭を離れません。
数日後、トキが松江の町を歩いていると、道端に座る物乞いの女に目を留めます。それはなんと、かつての母・タエでした。衝撃を受けたトキは、家族にも言えずに胸を痛めます。さらに、司之介の勤める牛乳屋に現れた三之丞が「自分を社長にしてほしい」と訴えて追い返される姿を目撃。雨清水家の没落を知り、トキは改めて家族の現実を痛感します。
夜、松野家ではわずかな彩色画の収入でしじみ汁を囲み、笑い合う家族の姿がありました。けれど、トキは母の姿が脳裏を離れません。
翌朝、花田旅館近くの新しい住まいへ向かい、錦織に向かって静かに告げます。
「……ヘブン先生の、女中になります」
\6週の解説動画はこちら/

第6週の感想・見どころは…?
- 「ラシャメン」と呼ばれた女性たちの現実
異人に仕えることが“恥”とされた明治社会で、差別と誇りのはざまで生きた女性たちの葛藤が描かれる。 - タエとトキの母娘の再会
「生きるために落ちぶれた母」と「誇りを手放せない娘」。二人の対比が胸を打つ。 - トキの決断と“働く女性”の始まり
支度金20円、月給15円。そのうち10円を借金返済に充て続けた――史実のセツが選んだ“生きる道”が重なる。
この週のエピソードは、小泉セツと実母チエ(=タエ)の実話に強く基づいています。弟・藤三郎(=三之丞)はオウムの商売に失敗し、150円という多額の借金を抱えました。
セツは家族を救うため、ハーンのもとで働くことを決意。支度金20円を受け取って借金返済に充て、月給15円のうち10円を返済に回し続けたと伝えられています。(明治24年当時の1円=約5,000円とすると、支度金20円は現在の約10万円)
また、「ラシャメン」は「羅紗=西洋の毛織物」に由来し、“異国に仕える女”を軽蔑する言葉として使われました。それでもセツは、家族を守るため、偏見を恐れずハーンの女中となり――やがて“妻・小泉セツ”として歴史に名を刻むことになります。
\史実の参考図書はこちら/
第7週「オトキサン、ジョチュウ、OK?」(11月10日〜):視聴率15.7%
錦織が改めてヘブンにトキを紹介すると、ヘブンは「シジミサン、ノー!」と首を振ります。「士族の娘ではない。しじみ売りだ!」と断言し、トキの逞しい手足を見て百姓の娘だと決めつけたのです。
しかし錦織が「ラストサムライ(勘右衛門)の孫です」と説明すると、ヘブンの表情が一変。ひと月分の給金20円を渡し、握手を交わしました。
トキは家族には「花田旅館でヘブン先生目当ての客が増え、人手が足りないため女中として雇われた」と作り話をします。その帰り道、松江大橋で三之丞を待ち伏せし、「これでおば様を助けて」と10円を渡しました。
翌朝、初出勤のトキはウメに教わりながら仕事を覚え、夜になるとヘブンと二人きりに。覚悟を決めていたトキに、ヘブンは「イキマショ… キョウ、オワリ」とだけ告げ、帰宅を促します。誤解されたままの不安と安堵が交錯する夜でした。
しかし家に戻ると、借金取りの銭太郎が現れ、トキが差し出した一円札5枚に家族は驚愕します。翌日、町で見かけたタエはまだ物乞いのまま。フミは松江新報で「ヘブンは旅館から引っ越していた」と知り、トキの行動を不審に思い始めます。
一方、松江新報の記者・梶谷は雨清水家を取材しようと廃寺を訪ね、三之丞から口止め料として一円を受け取ります。金の出所を疑うタエに、三之丞は「実は社長になりました」と嘘をつき、安心させようとしました。
その頃、トキを尾行した家族がヘブンの家に踏み込み、「異人の妾になったのか」と詰問。フミの叱責にトキは「暮らしのために仕方なかった」と告白します。錦織が“女中の意味”と説明すると、ヘブンは激怒。「私をそんな男だと思っていたのか!」と声を荒げました。誤解が解け、トキとフミは畳に崩れ落ちます。
その帰り道、家族は破れ寺で倒れているタエを発見。翌朝、トキは事情をすべて話し、三之丞が訪ねてくると9円を返そうとする彼を必死で止めます。「おば様を助けたいなら、自分を捨ててこれを受け取って」と訴え、フミも叱咤。ようやく三之丞は金を受け取りました。
こうしてトキは、松野家と雨清水家、二つの家族を支える“働く女性”となっていきます。
\7週の解説動画はこちら/

第7週の感想・見どころは…?
- トキの覚悟と誤解の連鎖
異人に仕えることへの偏見と、家族の誇りの衝突。トキが選んだ道は“生きるために働く”明治の女性像そのもの。 - ヘブンの人間味と文化のすれ違い
“士族の娘か否か”で人を測ろうとする偏見、しかしその奥にあるのは理解への戸惑い。異文化の壁がリアルに描かれる。 - 母タエと三之丞の悲哀
貧困の果てに虚勢を張る三之丞、物乞いとなる母タエ。トキの優しさと対照的に、明治社会の厳しさが浮き彫りに。
この週の物語は、小泉セツとラフカディオ・ハーン(小泉八雲)夫妻の史実を忠実に反映しています。
- セツが女中となった実話
1891年(明治24年)、セツは弟・藤三郎の借金150円を返すため、ハーンの家に住み込み女中として入ります。当時「外国人の女中=洋妾(ラシャメン)」と蔑まれていましたが、家族のために偏見を承知で働きました。 - “士族の娘ではない”と疑った逸話
ハーンは最初、セツの手足を見て「百姓の娘だ」と疑ったと伝えられます。のちに事情を知り、「その手足こそ孝行の証」と語ったという逸話が残ります。 - 出雲大社参拝=結婚の象徴
翌年、ハーンは西田千太郎とともに出雲大社を訪れ、セツも同行。これが日本式の婚礼を意味したとされています。
\ハーンの通訳、西田千太郎(錦織のモデル)の史実はこちら/
第8週「クビノ、カワ、イチマイ。」(11月17日〜):視聴率15.9%
新しい暮らしが始まったヘブンとトキ。英語の通じない生活に、ふたりはさっそく試練を迎えます。
ある日、ヘブンが「ビールが飲みたい」と伝えますが、英語の”beer”を聞き取れないセツは、「琵琶」「独楽」「ごま」など全く違うものを差し出し失敗。ようやく瓶の絵を見てビールと理解し、山橋薬舗から購入してきますが、勢いよく振って開栓したため、泡がイライザの写真にかかり、ヘブンは大激怒。
そんなトラブルを経ながらも、ふたりの関係は徐々に変化。夜な夜な執筆するヘブンのために、トキは蚊帳を吊るし静けさを守り、彼の心に少しずつ寄り添います。
さらにヘブンの期待に応えようと、トキは実母・タエのもとを訪ね、生け花の稽古を再開。ある日トキがいけた花に「美しい」と声をかけるヘブンの表情からは、少しずつ築かれる信頼が垣間見えます。
後半では、生徒の錦織兄弟らがヘブンの借家を訪れ、”ヘブンクイズ”が開催。イライザの写真について問おうとした錦織を、トキが制止する一幕も。するとヘブンは「シジミサン、チャンピオン!」と微笑み、トキに“ヴードゥー人形”を贈るという奇妙なプレゼントを贈ります。
\8週の解説動画はこちら/

第8週の感想・見どころは…?
- 英語と文化のすれ違いから始まる交流
言葉の壁による誤解と失敗が、やがてお互いを知る「きっかけ」となっていく。生け花や蚊帳など、日本文化の細やかな心配りを通して信頼が芽生える様子が丁寧に描かれる。 - 「ヴードゥー人形」の史実的背景
奇妙に見える“ヴードゥー人形”の登場には、史実の小泉八雲のアメリカ時代が影を落としています。八雲(ラフカディオ・ハーン)は青年期にニューオーリンズで暮らし、クレオール文化とヴードゥー教に強く惹かれました。
彼は「ヴードゥーの女王」マリー・ラヴォーの元を訪ね、黒人霊術や民間信仰を丹念に取材。実際にヴードゥーを題材としたエッセイや小説も執筆しており、呪術や霊界の描写に造詣が深かった人物です。 - ヴードゥー人形の本来の意味とは?
現代では“呪いの道具”としてイメージされがちなヴードゥー人形ですが、もともとは「守護」「願い」「癒し」のために使われるものでした。病気の治癒、恋愛成就、家族の安全を祈って作られたもので、黒魔術的な使い方は欧米の誤解・演出によって生まれた側面が大きいといわれています。
ドラマのトキも「丑の刻参りみたい。あー、早く呪いたいなぁ」と言っていましたが、実際のヴードゥー人形はより温かく民俗的な意味を持つもの。朝ドラが“人形=呪い”というステレオタイプを描きつつ、史実に基づいた教養を忍ばせた点は見逃せません。
ヘブンがトキに贈った「ヴードゥー人形」は、八雲がかつてニューオーリンズで実際に出会った信仰・文化に由来すると思われます。
小泉八雲は、当時差別されていたヴードゥー信仰にも真摯に向き合い、そこに宿る人々の心と力強さを伝えようとしました。日本では“妖怪”や“怪談”の作家として知られる彼が、民間信仰や異文化に対しても偏見なく向き合っていた背景を、朝ドラは象徴的に描いています。
トキとヘブン、文化も言葉も違うふたりが、少しずつ心を通わせていく様子は、史実のセツと八雲の関係とも重なります。言葉ではなく、行動で、感性で、心を伝える――そんな交流の原点が詰まった第8週でした。
第9週「スキップ、ト、ウグイス。」(11月24日〜):視聴率15.7%
冬の松江。ひと月ほどが過ぎたある日、ヘブンは島根県知事・江藤に招かれ、旧松江藩主・松平家の菩提寺である月照寺を訪ねます。同行したのは、東京の女学校で英語を学んだ江藤の娘・リヨ。彼女はヘブンに積極的に英語で話しかけるも、ヘブンは寺の大亀の石像に夢中で、まったく相手にしません。
数日後、リヨは「日本らしい贈り物を」と、鳥かごに入ったウグイスを手にヘブンの家を訪ねます。トキに想いを打ち明け、「協力してほしいの」と頼みます。トキは戸惑いながらも承諾するが、一方で江藤は「ヘブン先生は一年契約、妙な関係にならぬよう力を貸してくれ」と錦織に依頼。錦織はトキに「恋仲にならないよう邪魔をしてくれ」と懇願し…。トキは板挟みになり、苦しい立場に立たされます。
土曜の午後、ヘブンが不在のあいだ、リヨはトキを八重垣神社に誘い、鏡の池で恋占いを行います。「ヘブン先生は遠くの方だから、舟は遠くで沈むのよね」と言うリヨに、トキは心の中で「沈んで…沈むな…」と祈ります。舟は遠く対岸で沈み、リヨは「ベリーベリーハッピー!」と歓喜。しかし傍らでは、トキの祖父・勘右衛門までもが恋占いをしており、「沈め!沈んじょくれ!」と叫ぶ声にトキは仰天します。
翌日曜日、ヘブンとリヨは島根県庁や城山稲荷神社を見学。遠くから江藤と錦織が見張るが、ヘブンは神社に並ぶ石の狐像に夢中になり、リヨを完全に忘れてしまいます。
夜、トキは書斎の火鉢に炭を足し、ヘブンが滞在記の執筆に集中する姿を見守ります。ヘブンはイライザの写真に向かって「松江は本当に素晴らしい街。いつか君と歩きたい」と語りかけるのでした。
\9週の解説動画はこちら/

第9週の感想・見どころは…?
- リヨとトキ、“恋の板挟み”ドラマ
トキはリヨの恋を応援しながら、錦織に頼まれてそれを止めなければならないという難しい立場に。朝ドラらしい人間模様に、松江の名所を絡めた情緒的な描写が光ります。 - 勘右衛門の“恋占い”がまさかの参戦!?
シリアスな恋模様の中に挟まる勘右衛門のコメディシーンが絶妙。老境にして恋する姿は、物語のユーモアと温かみを添えています。 - リヨの恋と八雲の“届かない想い”の対比
リヨがヘブンに恋をし、ヘブンは遠く離れたイライザ(ビスランド)に想いを馳せる。交わらない恋の構図が、物語に深い余韻を残します。 - 月照寺と“テイ坊”の伝説へとつながる布石
月照寺の登場は、のちに八雲が「神々の国の首都」で記す“松江の霊性”や、小泉セツの母チエが体験した「テイ坊伝説」へと続く重要な伏線です。
- リヨ=籠手田安定の娘説
ドラマの江藤知事のモデルは島根県知事・籠手田安定。彼は剣術心形刀流の免許皆伝を持つ豪傑で、松江在任中は三女・淑(よし)と四女・従(じゅう)と暮らしていました。八雲は籠手田邸に招かれ、娘たちとも交流した記録があり、リヨのモデルはこのどちらかと推定されます。 - ハーンが松江に招聘された経緯
当初、英語教師として招聘されたのはアメリカ人エドウィン・ベーカーでしたが、籠手田知事は宗教的対立(キリスト教 vs 神道)を懸念して契約を取り消し。代わりに選ばれたのがラフカディオ・ハーンでした。この偶然の連鎖が、八雲と松江を結びつけたのです。 - “すれ違う恋”の史実背景
八雲がイライザ(エリザベス・ビスランド)に恋心を抱いていたことは史実として知られています。彼女はアメリカで活躍するジャーナリストで、ハーンは思いを伝えぬまま日本へ渡航。ドラマで描かれた“写真に語りかけるシーン”は、この実話を下敷きにしています。 - 月照寺と“テイ坊”の不思議な逸話
小泉セツの母・チエが体験した「月照寺のテイ坊」伝説も史実に基づくもの。助けた狐が人の姿で恩返しに来たという逸話は、後の八雲の怪談世界につながっていきます。
第10週「トオリ、スガリ。」(12月1日〜):視聴率15.8%
寒さが増す松江。夜中に執筆していたヘブンは、ついに気管支カタルで寝込んでしまいます。その最中、訪ねてきたのが松江中学の生徒・小谷春夫。授業でヘブンにすっかり心酔し、今や“ヘブン信者”のような存在に。そしてどうやら、トキに淡い恋心を抱いているようで――?
サワから小谷がトキに想いを寄せていることを聞いた松野家は、トキの婿候補と期待。しかし、春夫は中学生、トキは22歳の離婚歴あり。果たして、二人の恋の行方はどうなるのでしょうか。
トキをデートに誘った小谷でしたが、清光院デートでトキの怪談オタクっぷりを見て“付いていけない”とドン引き。周囲の先走りをよそに、小谷の恋は静かに終わりを迎えたのでした。
\10週の解説動画はこちら/

第10週の感想・見どころは…?
- “地獄のような松江の冬”と、体調崩したヘブン
小泉八雲が実際に体験した寒さと病――気管支カタルは史実にも残る重い風邪の一種で、療養中に彼はセツと出会いました。ドラマでもそのエピソードが忠実に描かれ、史実とフィクションが自然に重なっていきます。 - “婿候補”小谷春夫の意外なモデルとは?
春夫のモデルとされるのは、八雲の教え子・大谷正信と藤崎八三郎。前者は後に八雲全集の翻訳・編集を担い、後者は八雲の絶筆の手紙を受け取った軍人。春夫の“八雲愛”と真っ直ぐな眼差しは、これらの弟子たちの象徴です。
- 年の差&身分差婚の明治的リアリティ
トキは22歳で離婚歴あり、一方の春夫は松江中学の学生。この“年の差”に戸惑う現代的視点に対し、明治期では「13歳から結婚可能」「婿養子制度が普及」「再婚も比較的自由」など、時代背景に根差した柔軟な婚姻観があったといわれています。 - 『本邦諸国奇談集』と怪談文化の萌芽
10週で取り上げられたのは、江戸後期の怪異文学。幽霊、怪異譚、恋の執念など、八雲が後に描く怪談世界の“種”が詰まった一冊であり、トキの“物語への愛”を結びつける象徴的アイテムでもあります。 - セツ=トキとの“再出発”のはじまり
気管支カタルという病を機に、セツ(トキ)と八雲(ヘブン)は初めて“同じ時間”を過ごしはじめます。物語としての転機はもちろん、史実のふたりが出会った瞬間も丁寧に重ねられ、まさに“冬の松江で芽吹く春”のような回でした。

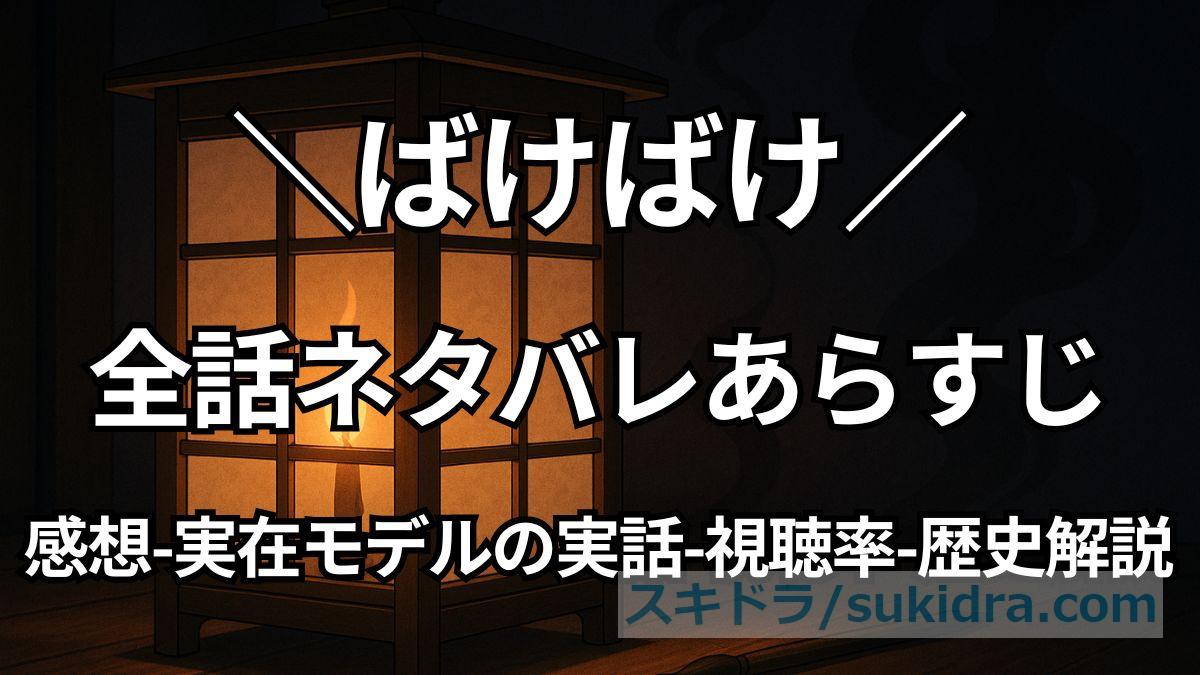



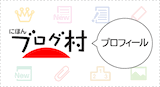

コメント