朝ドラ『あんぱん』第16回で描かれた、のぶ・嵩・千尋の「通知表」シーン。そこに並んでいた評価――「甲・乙・丙・丁(こうおつていへい)」に、思わず「なにこれ!?」と驚いた視聴者も多いのではないでしょうか。
実はこの4文字、昭和初期の学校で実際に使われていた成績評価制度。現代でいう「5・4・3・2・1」や「ABC評価」のルーツともいえる仕組みなんです。
本記事では、
…といった、ドラマを見て気になったことを全部まるごとわかりやすく解説していきます。
のぶの「体育だけ甲」、嵩の「図画だけ甲、数学は丁」、千尋の「オール甲」――この通知表に込められた昭和という時代のリアルを、じっくりひもといてみましょう。

今のような小学校・中学校が義務教育になったのはいつから?のぶと嵩のように進学している人は珍しい?旧制学校の疑問をまるっと解消しよう。
通知表「甲乙丙丁」の意味は、成績4段階(ABCD)評価
ドラマ『あんぱん』第16回で、のぶ・嵩・千尋の通知表が登場しました。そこで出てきた成績評価の記号――それが「甲乙丙丁」です。

甲乙丙丁って…なんか漢文の成績みたい!実はこれ、昭和の通知表では当たり前だったんだよ。
この「甲乙丙丁(こう・おつ・へい・てい)」は、昭和初期まで実際に使われていた成績の4段階評価。1意味としては、甲が最も良くて、丁が最も悪いという、現代で言うと次のような感じです。
| 評価 | 意味(当時) | 現代の感覚で言うと |
|---|---|---|
| 甲 | 非常に優秀 | A・5(最高評価) |
| 乙 | 優れている | B・4 |
| 丙 | 普通(まずまず) | C・3 |
| 丁 | 不十分/劣っている(要注意) | D〜E・2〜1 |
現代の5段階評価と照らし合わせると、甲=5、乙=4、丙=3、丁=1〜2に相当すると考えるとイメージしやすいですね。ただし、昭和当時は相対評価ではなく「絶対評価」が基本。

つまり、“全員甲”も、“全員丙”もありえるってこと。教師の判断がすごく大きかったんだね。
のぶのように、裁縫や数学が「丙」だらけでも体育が「甲」ならOK…という、「光る科目」がちゃんと評価される柔軟さも、昭和の通知表にはあったのです。
🏃♀️#きょうのあんぱん🖌
— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) April 20, 2025
女子師範学校合格に向けて猛勉強を始めたのぶ!
しかし、成績が振るわず…。
嵩も通知簿の評価が低く、それをたしなめる千代子と、やればできると諭す登美子です😓#今田美桜 #北村匠海 #中沢元紀 #戸田菜穂 #松嶋菜々子#朝ドラあんぱん pic.twitter.com/aKGsOX3uSZ
いつまで使われていた?「甲乙丙丁」の評価制度の変遷
「甲乙丙丁」って、今ではあまり見かけませんよね。実はこれ、戦前教育の象徴ともいえる成績表記でした。
ところが、昭和13年(1938年)に成績評価制度が大きく改訂されます。2
- 数学や国語など主要教科は「10点満点評価」に
- 道徳や生活態度などは「優・良・可」の3段階評価に
- 通知表のフォーマットも全国で統一化が進むように
こうして「甲乙丙丁」は徐々に姿を消し、昭和16年頃には“旧制度”扱いになっていきました。
さらに戦後の学制改革で、「6・3・3制(小中高)」が導入されると、現在のような「5段階評価(5〜1)」が定着。今では、通知表に漢字4文字がズラリと並ぶなんて、なかなか見ないですよね。

そう考えると、のぶたちの通知表は、ほんと“時代”が詰まってるなぁ…。教育って社会の写し鏡だね。
旧制中学校・高等女学校の学年は今で言うと何年生?
「高等女学校5年生」「旧制中学校5年生」って、今で言うと…何年生?という疑問、ありませんか?
ドラマではのぶが「高女5年生」、嵩が「中学5年生」として通知表を受け取っていました。
実はこれ、戦前の学制(旧制)による表現。今の「中学→高校」とは違う仕組みなんです。
🏃♀️#きょうのあんぱん🖌
— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) April 11, 2025
あっという間に年月は流れ…
のぶは高等女学校の4年生になりました🙌
🔻大きくなったのぶ・嵩・千尋のシーンをもう一度👀https://t.co/S1PPZz7DgH#今田美桜 #北村匠海 #中沢元紀#永瀬ゆずな #木村優来#朝ドラあんぱん pic.twitter.com/0e48wRzgiE
昭和初期の学年制度(旧制)と今の学年対応表
| 学校名 | 入学年齢 | 修業年限 | 今で言うと |
|---|---|---|---|
| 尋常小学校 | 6歳 | 6年 | 小学校1〜6年生 |
| 高等小学校 | 12歳 | 2年 | 中学1〜2年相当 |
| 旧制中学校(男子) | 12歳 | 5年 | 中学1〜高校3年相当 |
| 高等女学校(女子) | 12歳 | 5年 | 中学1〜高校2〜3年 |
| 師範学校・高等学校 | 17歳前後 | 3年 | 専門・大学予科相当 |
つまり、のぶ(高女5年)=現代の高校2年〜3年生、嵩(旧制中学5年)=高校3年生相当ということになります。

“中学5年生”って言われると、中学なの?高校なの?って混乱するけど…この頃は“中学校”が5年間あって、高校とセットだったんだね◎
このような「中等教育5年制」は戦後に廃止され、現在の「中学3年+高校3年」の形に移行しました(学制改革:1947年以降)。3
成績が進学・就職に与えた影響とは?
昭和初期の教育において、成績は“将来を左右する”大きな要素でした。「甲乙丙丁」で言うと、進学の鍵は“甲”または“乙”をいかに多く取れるか。とくに「甲中心」は、上級学校への進学には必須とされました。

裁縫も丙、数学も丙…って、それで師範学校受けるの、のぶちょっと無謀じゃない!?なんか、先生が声をかけた理由が分かったよ…。

志“は”立派って言われていたもんね。先生、苦笑気味だったよ(笑)。運動のみ“甲”って…体育教師コースでワンチャンかも?
一方、嵩のような男子が目指せる進学先は「旧制高等学校→帝国大学」という超エリートコース。ここでも“甲”中心の成績が求められました。特に理系進学を考えるなら、数学や理科で“丙以下”は致命的。嵩が数学で「丁」を取ってしまったのは、まさにその危機を表しています。
また、通知表の成績は、就職にも大きく関係していました。戦前は学校が就職のあっせんをすることが多く、成績上位者から推薦されていくのが一般的。推薦状(いわば“保証書”)を得るには、評定「乙」以上が並んでいることが条件だったとも言われています。
昭和10年前後の進学率は20%弱!男子と女子、進路の違い
昭和10年当時、小学校卒業後に中等教育(旧制中学・高等女学校など)へ進学できた子どもは、男子で約20%、女子では約16%程度でした4。

女子の進学率が低いのはもちろんだけど、男子も低…っ。“女に学問はいらん”って、かまじいが言うのも納得かも。
さらに進学率には、家庭の経済力・地域・性別といった格差が大きく関係していました。
のぶのように、石工の娘でありながら高等女学校に通っているというのは、かなり稀なケース。それだけ学業が優秀だったのか、あるいは“女でも学ばせたい”という父親・結太郎の意志が強かったのかもしれません。
高等女学校を卒業した後の進路は、ほとんどが以下のいずれかでした。
- 就職(郵便局、電話交換手、裁縫教師など)
- 結婚(在学中に縁談が決まるケースも)
- 師範学校・女子専門学校への進学(ごく一部)
その中でのぶが選ぼうとしている「3」は、明らかに“ハードモード”です。

蘭子が高女へ進まず郵便局へ就職したのは、当時では普通の進路ってことだね。高女へ通っているのに、何でのぶは成績が悪いのか謎だね…。
小学校卒業後、中等教育に進むには「入学試験」があった
当時の教育制度では、小学校(尋常小学校5)卒業後に進学できる中等教育機関は次の4種類。
| 種類 | 対象 | 修業年限 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 旧制中学校 | 主に男子 | 5年 | 現代の中高にあたる(難関) |
| 高等女学校 | 主に女子 | 5年 | 学歴の頂点、進学率は低め |
| 実業学校(商業・工業など) | 男女 | 3〜5年 | 就職前提。実務系 |
| 師範学校 | 男女(上位層) | 3〜5年 | 教員養成、狭き門 |
これらの学校に進学するには、各校の入学試験(学力試験)に合格する必要がありました。試験科目は主に「国語・算術・修身」などで、学校によっては作文や面接が課されることも。
推薦や成績枠もあったけど、基本は“試験突破”が必要
一部には、小学校長や教師の推薦を受けて「試験免除」や「加点」される“優等生枠”のような制度があった地域もありますが、これは例外的。ほとんどの子どもたちは、公立・私立問わず試験を受けて競争を勝ち抜く必要がありました。678

調べれば調べるほど、嵩とのぶが進学できたのが疑問だよ…。小学校から中高と進学すると勉強のレベルが全く違うってことかな?
🏃♀️#きょうのあんぱん🖌
— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) April 13, 2025
朝田石材店にパン屋が併設されて8年が経ちました🍞
のぶは、高等女学校の5年生、最終学年になりました。
次女の蘭子は、地元の郵便局勤め。
三女のメイコは、高等小学校の1年生です。#今田美桜 #江口のりこ #河合優実 #原菜乃華 #阿部サダヲ#朝ドラあんぱん pic.twitter.com/eA9sBvFt11
高女や旧制中学は“狭き門”だった
昭和10年時点の中等教育への進学率は、男子20%、女子16%程度(※前述)。つまり、80%以上の子どもが進学できなかった時代です。

進学するだけでもすごいことで…のぶや嵩は、“受験を突破してきたエリート”ってわけだね◎
のぶや嵩が高女・中学に通えていたのは、本人の成績・家庭の理解・そして運のすべてがそろった結果だったのかもしれませんね。
『あんぱん』の成績描写がリアルで泣ける…!3人の通知表まとめ
ドラマ『あんぱん』第16回では、のぶ・嵩・千尋の通知表が映されました。これがまた、性格と将来の道筋をリアルに映す“成績ドラマ”そのものでした!
| 生徒名 | 得意科目・評価 | 苦手科目・評価 | 総評/将来性 |
|---|---|---|---|
| のぶ | 体育(全学期「甲」) | 数学・裁縫・理科(「丙」中心) | 明るく活発だが勉学は平凡。師範学校合格は厳しい…? |
| 嵩 | 図画(常に「甲」)、歴史・地理で一部「甲」 | 数学(ついに「丁」)、理科(「丙」) | 美術センス抜群。学力面は不安、家族の期待とギャップ大 |
| 千尋 | 修身・国語・理科・体操・数学(ほぼ「甲」) | 図画・歴史のみ「乙」 | 全教科で安定のトップ。将来有望な秀才タイプ |

嵩の数学“丁”に一番驚いてたの、家族じゃなくて視聴者だと思う(笑)。小学生の嵩ちゃんは超成績優秀だった印象だもんね~。

今では、テスト中に漫画を描くほどの度胸が(笑)。対して千尋、リアルに“オール甲”でパーフェクトすぎる…!
3人の通知表がそれぞれの将来や葛藤を象徴しており、昭和の「成績=人生の道筋」のリアルさがよく表れた名シーンでした。
🏃♀️#きょうのあんぱん🖌
— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) April 21, 2025
夜、嵩は寛と千尋の会話を聞いてしまいます。
「千尋……おまん、ひょっとして、嵩のために、医者になるがをやめたがやないか?」
🔻きょうの放送を見る👀https://t.co/xiNdtU8B7U#北村匠海 #中沢元紀 #竹野内豊#朝ドラあんぱん pic.twitter.com/YGPxAwJYxi
よくある疑問:甲乙丙丁って結局どういう評価?まとめて解説
ここからは、『あんぱん』を見ていて気になる疑問をQ&A形式で解説します。
- Q「甲乙丙丁」はいつごろまで使われていたの?
- A
昭和13年(1938年)頃から、主要教科に10点満点評価、生活態度などには「優・良・可」の評価が導入され、「甲乙丙丁」は少しずつ姿を消していきました。戦後の学制改革(1947年以降)で完全に廃止され、現在の「5段階評価(5〜1)」に移行しました。10
- Q女子師範学校って今でいうとどんな学校?
- A
簡単に言えば「教員養成に特化した短期大学or専門学校の先駆け」です。女子師範学校は、当時の女子教育の最高峰。
卒業するとそのまま小学校教員として任用されるケースが多く、いわば“女性エリート養成校”のような位置づけでした。戦後の学制改革で、現在の国立大学の教育学部に引き継がれた学校もあります。
- Q「丁」ってどれくらいやばい成績?
- A
かなりまずいです…!「丁」は最下位評価で、当時は「落第(留年)対象」にもなりうるレベル。
昭和初期では、実際に“丁を連続して取ったら進級不可”という校則も存在しました。嵩の通知表に「数学=丁」が記され、伯母の千代子が青ざめていたのも納得ですね。
- Q昔の通知表にはコメントや所見欄はなかったの?
- A
所見欄は存在していましたが、現在のような「担任の一言メッセージ」的な柔らかい記述ではなく、やや形式的で評価中心の文章が多かったようです。
例:「学業に精進の様子見ゆ」「操行良好にして同輩に信頼さる」など、まるで漢詩のような言い回しが特徴的です。
- Q「中学5年生」って結局中学生?高校生?
- A
「旧制中学5年生」は、現代で言う高校3年生相当です。当時は「中等教育=5年制」の1本通しだったため、「中学3年→高校1年」という今のイメージとは異なります。「高等女学校5年」も同様に、高校2〜3年生レベルの年齢・カリキュラムでした。
- Q『あんぱん』で実際のモデルになった人物(小松暢・やなせたかし)も、通知表がこんな感じだったの?
- A
はい。嵩のモデルであるやなせたかしさんは、幼少期から絵が得意で学業はそこそこ。弟・千尋さんは勉強もスポーツも万能な秀才タイプだったと言われています。『あんぱん』の通知表描写は、モデル兄弟の性格や人生と重なる部分が多いんです。
- Q義務教育が今と同じ9年(小学校6年、中学校3年)になったのはいつから?
- A
昭和22年(1947年)から、義務教育9年(小学校6年、中学校3年)と規定。11
同時に、「中等教育5年制」は戦後に廃止され、現在の「中学3年+高校3年」の形に移行しました。

“中学5年生”って響き、やっぱり混乱するよね。でも、これを知ってるだけで昭和ドラマが何倍も楽しめる気がする◎
🏃♀️#来週のあんぱんは?🖌
— 朝ドラ「あんぱん」公式 (@asadora_nhk) April 20, 2025
第4週「なにをして生きるのか」予告動画🎥
「女子師範学校」合格へ向けて勉強をし始めた、のぶ。一方、進路に悩む嵩は…
🔻あらすじはコチラ📖https://t.co/ih4WaW0A4I#今田美桜 #北村匠海#朝ドラあんぱん pic.twitter.com/ETJ4GWQSOj
まとめ:『あんぱん』から見る昭和の教育制度と“生き方”の選択肢
『あんぱん』の通知表シーンをきっかけに、昭和初期の教育制度のリアルが見えてきました。
- 成績は「甲・乙・丙・丁」の4段階。
- 進学できるか、就職できるか、そしてどんな人生を選べるか。
- そのすべてが、通知表1枚に込められていた――そんな時代だったのです。

“成績がすべてじゃない”って言われる現代と真逆の時代。だからこそ、のぶや嵩の迷いや努力が沁みるのかもしれないね。
昭和の時代背景を知ると、『あんぱん』という物語の重みも変わって見えるはず。今後の展開でも、彼らの「通知表の先」にある選択と成長を、ぜひ見届けてください。
\あわせて読んで理解度アップ/
≫【あんぱん登場人物・年齢早見表】のぶと嵩、千尋・蘭子・メイコは今何歳?
参考文献、資料:
- 昭和初期の教育資料/国会図書館レファレンス事例、甲乙丙丁とは?教育史上の評価制度の変遷(国立国会図書館) ↩︎
- 国立教育政策研究所/学制改革史資料(→昭和の教育評価と通知表) ↩︎
- 日本の学制百年史(文部省) ↩︎
- 日本の学制百年史(文部省) ↩︎
- 尋常小学校:明治維新から第二次世界大戦勃発前までの時代に存在した初等教育機関の名称(Wikipedia) ↩︎
- 日本の学制百年史(文部省) ↩︎
- 昭和教育史資料集(国立国会図書館リサーチ) ↩︎
- 旧制中等教育制度の変遷と試験制度、我が国の学校教育制度の歴史について(国立教育政策研究所) ↩︎
- 我が国の義務教育制度の変遷(文部科学省) ↩︎
- 国立国会図書館レファレンス|成績評価の変遷 ↩︎
- 我が国の義務教育制度の変遷(文部科学省) ↩︎



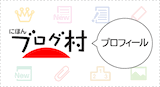

当サイトでは、話題の好きなドラマ情報をお届けします。
原作(小説・漫画・アニメ)のあらすじ・ネタバレ感想、ドラマのあらすじ・ネタバレ感想、原作との違い、原作書籍や配信先を紹介します。
推理小説好きなので、ミステリー要素がある作品が多くなるかも?気になる作品をピックアップしていきます。
他にもタイドラマのサイトを運営しているので、興味のある方は下記のサイトマークから覗いてみてください♡