江戸時代の大分県竹田市を舞台にした赤神諒の小説『はぐれ鴉』。仇討ち、隠れキリシタン、妖怪伝承…フィクションながら、史実との接点が随所に散りばめられた“考察型”時代ミステリーです。
本記事では、
…といった疑問に答えるべく、作品と史実の接点を徹底解説。
舞台となった岡藩(竹田藩)の歴史や、実在のキリシタン伝承、作中アイテムの考察まで――原作小説やドラマで結末を知ったあなたが、“もう一度見返したくなる視点”をお届けします。

TOSテレビ大分開局55周年でドラマ化!主演・神尾楓珠×仇敵(はぐれ鴉)役・椎名桔平さん✨大分県内のロケ地巡りもしてみたい~!
【実話検証①】『はぐれ鴉』は実話がモデル!大火事は実際にあった
歴史小説を読むときに気になるのが、どこまでが実話でどこからがフィクションなのか?あるいは全て作者の歴史的解釈をふまえたフィクションで、時代設定だけが小説に取り込まれているのか?気になるところです。
舞台は実在の「竹田藩」!現在の大分県竹田市とは?
物語の舞台・竹田藩は、江戸時代に実在した「岡藩(中川氏)」がモデルです。場所は現在の大分県竹田市。九州の山間に位置し、城下町や温泉、神社仏閣が今も残る歴史情緒あふれる町1です。
中川氏は豊臣秀吉の家臣・中川清秀の流れをくむ大名家で、1601年から明治維新まで岡藩を治めました。作中でも語られるように、この地は外様大名の領地でありながら文化人や学者を招いた開明的な藩政が知られています。

岡城とか、今でも石垣が残ってて、すごくカッコイイ〜!“荒城の月”のモデルにもなったんだって!

“荒城の月”は、瀧廉太郎作曲、土井晩翠作詞した日本の名曲。岡城跡の下を走る国道502号の上りを走ると、この曲が流れるよ~。2
「城代一族郎党二十四人鏖殺事件」は、実在の大火事を利用した創作
『はぐれ鴉』の冒頭を飾るのが、城代一族二十名の鏖殺(皆殺し)事件。この衝撃的なエピソードは、フィクションです。ただし、「寛文6年の火災」3や「藩政の混乱」など、史実と符号する時代背景を丁寧に重ねて物語が構築されています。
一部では、作者が参考にした竹田市の“史実っぽい”事件があるのでは?という声もありますが、明確なモデル事件は確認されていません。
作者・赤神諒が語る「フィクションに史実を混ぜた理由」
赤神諒さんは『はぐれ鴉』について、「フィクションだけど“見える史実”があちこちに隠れている」と明かしています。これは、あくまでエンタメ小説として面白さを重視しつつ、歴史の奥行きや地域のリアリティを織り交ぜた、独自の作風。
竹田の市民や歴史ガイドの協力のもと、「地元の伝承」や「現存する遺物」をベースにした設定が随所に活かされており、読者の中には「これは本当にあった話かも?」と錯覚してしまうほど。

“一ツ眼鳥”とか“姫だるま”も実在するんだよね…?でも八尺女はさすがに妖怪伝説だからね(笑)
【実話検証②】竹田キリシタンとは?竹田藩とキリスト教の関係
小説やドラマで結末を知った方なら、なぜここまで隠さなければならないのか?と疑問に思うことも多々ある信仰宗教。江戸時代にキリスト教が弾圧されたのは知っているものの、いまいちピンとこないという方も多いのではないでしょうか。ここからは、竹田藩とキリスト教について見ていきましょう。
1612年、幕府は禁教令で布教を禁じる!江戸時代のキリスト教弾圧とは…
江戸幕府は、1600年代初頭からキリスト教の布教を厳しく禁じる「禁教政策」を実施しました。1612年の禁教令5に始まり、踏み絵や宗門改帳などを通じて「仏教徒としての証明」が義務づけられました。
作中で描かれる「隠された信仰」や「誰が味方か分からない緊張感」は、まさにこの歴史的背景に根差しています。
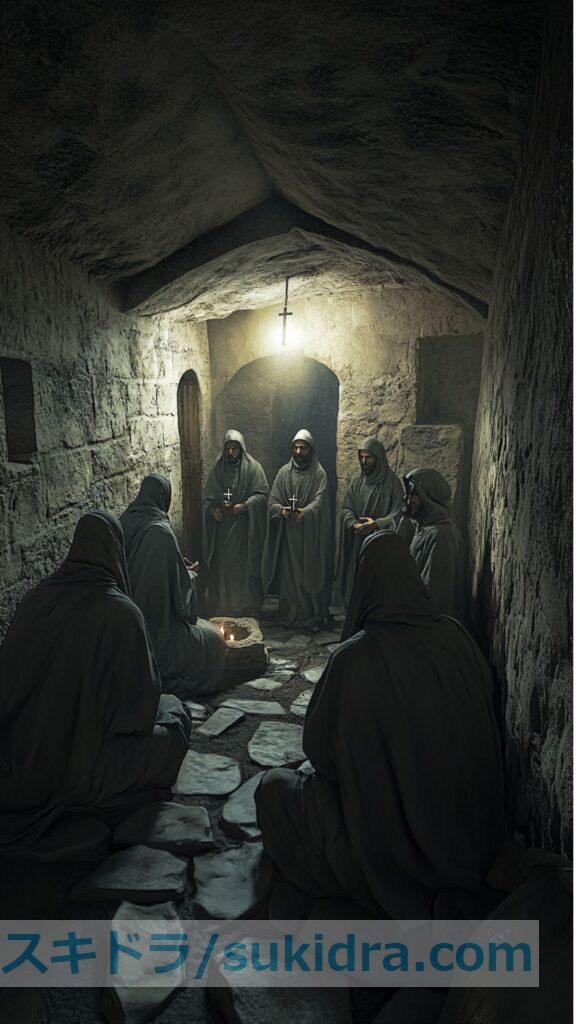
宗門改帳
しゅうもんあらためちょう江戸幕府がキリスト教禁制を徹底させるため,幕府直轄領はもとより私領 (大名の領分と旗本の知行所) の人民について,寺院にその檀徒であることを証明させた帳面。
引用:コトバンク

寺院を通じて全国民を仏教徒として管理し、潜伏キリシタンを監視する仕組み(寺請制度)が完成したんだね。
竹田藩に隠れキリシタンは実在したのか?
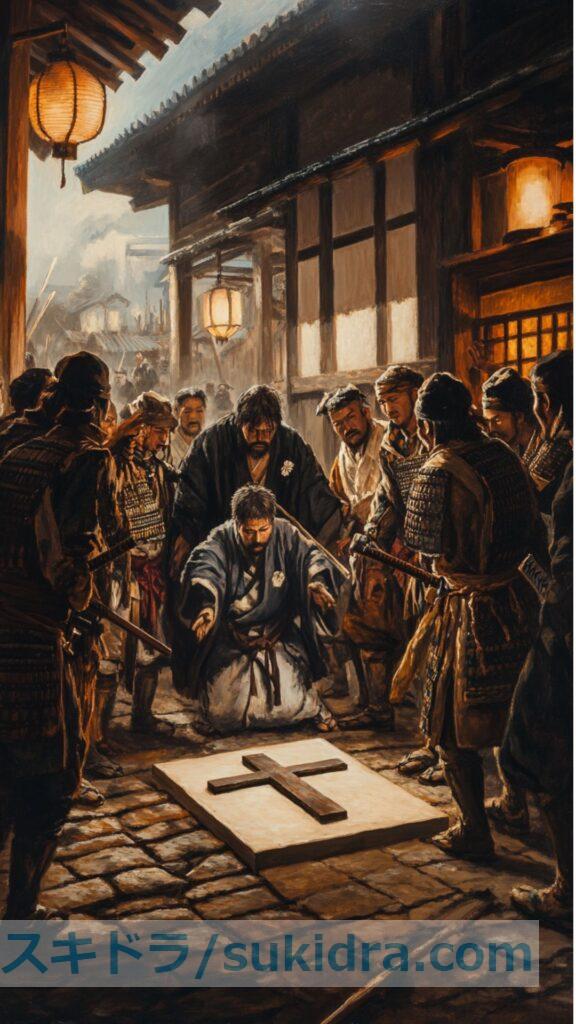
これは答えが「YES」に近いです。岡藩の初代藩主・中川秀成はキリシタン大名・高山右近の縁戚であり、領内にも信徒が多くいたとされています。
実際、竹田市の山中には「キリシタン洞窟礼拝堂」や「十字を刻んだ鳥形石像」など、キリスト教との関係をうかがわせる遺物が残っています。処刑者の数は非常に少なく、藩としては比較的「寛容」だったとも言われます。
ただし、それはあくまで“表向き”の話。信仰を続けるには常に命のリスクが伴ったことは想像に難くありません。

このイラストは踏み絵のシーンを描いたものだけど、作中では“洗礼に使った石の上に立つ”のはOKなんだって。理屈が分かるような分からないような…?

とにかく、色々工夫して踏み絵だけじゃなく外から来る(キリスト教ではない)よそ者の目を上手くあざむいていたんだね。
巧佐衛門の“自己犠牲”とキリスト教モチーフの共通点
作中で描かれる「はぐれ鴉」こと巧佐衛門の行動は、一見して非情な大量殺人。しかし、物語が進むにつれ、それが「誰かを守るための犠牲」であったことが明かされます。

はぐれ鴉の口からは、キリシタンって言葉が出てこなくても、“精神”がすごく伝わる話!“誰も見てなくても、誰かのために生きる”って、沁みるよね。
【実話検証③】岡藩は藩主中川もキリシタンだった!竹田キリシタンの歴史
岡藩藩主中川秀成は高山右近の従弟にあたり、先代の志賀親次(秀成の義父)も熱心なキリシタンでした。そのため、志賀氏・中川氏の時代を通じて竹田・朽網には信徒が多かったとされています。7
実際、1580年代に宣教師が訪れた記録があり、1604年には藩領内(現在の豊後大野市朝地町)に聖堂が建てられています。8
下記は有名な、竹田市殿町に残る隠れキリシタン洞窟礼拝堂。元和3年(1617年)に岡藩筆頭家老の屋敷裏に造られ、内部にはマリア像が安置されていたといいます。
今朝も4時30分から18kmほど走ってきました。
— 好いーと九州 (@suito_kyushu) June 15, 2022
せっかくなので今日は爽やかな朝らしい動画から。
瀧廉太郎も母に連れられ、姉と共に訪ねたキリシタン洞窟礼拝堂です。
静寂の中、鳥のさえずりと風の音だけが聞こえます。(1/2)#瀧廉太郎 #竹田 #キリシタン洞窟礼拝堂 #キリスト教 #遺産 pic.twitter.com/ezzjQAjkr6
幕府禁教令下でも岡藩は信徒を比較的保護し、殉教者数は三代~八代藩主の間で計44名にとどまったとされています。これは、豊後国全体で殉教者が約1000人(うち葛木地区で約200人)といわれる中で極めて少ない数であり、藩ぐるみで弾圧を「見せしめに最小限に抑えた」可能性が――。9
市内にはキリシタン関連の伝承・遺物が数多く残り、後世で様々な解釈がされています。
【実話検証④】物ノ怪は8割実話!『はぐれ鴉』の“史実らしき”要素を考察
驚くことに、作中の物ノ怪の類は実際に竹田で語り継がれているものなんだとか!どこまでが本当で、どこからが創作なのかを見ていきましょう。
「一ツ眼鳥」や「八尺女」は実在伝承!
物語のキーアイテムとして登場する「一ツ眼鳥」や「八尺女」。いかにも創作っぽく見えるこれらの存在、実はモデルとされるものが実在します。
――江戸から久しぶりに故郷に戻った才次郎は、人を食い殺す「一ツ眼烏」や、恋する女性に祟りをなす「八尺女」など物ノ怪の噂をいくつも耳にします。さらにお稲荷さんが数多くあったり、呪いの歌が聞こえてきたり、竹田中奇妙なことがいっぱいです。
これは八割方、竹田で語り伝えられているものなんですよ。こういう物ノ怪はいないですかと生き字引に確認すると、ちょうどいい話を紹介してくれるんですね。八尺女は文字通り背がすごく高い女の妖怪で、ヒロインの人生に影を落とす存在として登場させました。一ツ眼烏は、作品に書いた通りの石像が残っています。ネットで検索すると画像が出てきますよ。残り二割は創作。たとえばもぐら鳥という地中を走る鳥は、ストーリー上の必要があって私が作ったものです。
「一ツ眼鳥」は竹田市内に現存する“鳥をかたどった一眼の石像”が由来。鳥の形に丸いくぼみが彫られた不思議な石像で、観光ガイドなどでも“ミステリアス遺物”として紹介されています。10作中では“人を食い殺す”と伝えられる妖怪として描かれていますが、現地では悪霊というより“異国の鳥”や“霊鳥”として語られることが多いようです。
一方「八尺女」は全国に類似の妖怪伝承が存在します。主に長身の女性妖怪で、“目が合うと祟られる”など、恐怖系の都市伝説に近い存在。竹田市独自の伝承ではなく、赤神諒さんが汎用的な妖怪伝承をストーリーにうまく組み込んだものと思われます。

“八尺”って240cmくらい!現れたら腰抜かすよ…。でも、英里と関連があるって思うと、ただの怪談じゃない気も…?
英里の“異国の血”は何を意味する?
ヒロイン・英里は“南蛮人の血を引く”設定で、白い肌と青い目を持つ美しい女性。彼女の存在は物語全体に“異質さ”と“運命の重み”を与えています。
実際、戦国〜江戸初期の九州は、南蛮(ポルトガル・スペイン)との交流が盛んで、宣教師や貿易商が多数来航していました。長崎・大分などでは実際に“混血児”も存在していた記録があり、英里のような外見の女性がいても不思議ではありません。
英里の姿は、ただの美しさを象徴するだけでなく、時代の“宗教的異物”や“差別・排除”の象徴とも読めます。彼女の血と、父・巧佐衛門の秘密が交錯する構造は、まさにキリシタン時代の“表と裏”を映す鏡のようです。

本誌やドラマを見て大分に行くなら、「竹田 キリシタン」で検索すると面白い名所がいっぱい出てくるよ~。想像が膨らむ歴史も魅力の竹田市…!
竹田市の山の奥の洞内に「上坂田の磨崖仏」と呼ばれる謎の石像がある(磨崖神と呼ぶ人もある)。高さは2mを超え、直面して大きさに圧倒される。何より石仏の国大分でも他に類を見ない、この羽が生えたような異形の姿。隠れキリシタンにまつわるもの説や、修験道にまつわる鴉天狗ではという話もある。 pic.twitter.com/c1SoVMsUEv
— のんさん (@non_mintcar) August 20, 2022
実写ドラマのロケ地は大分!岡城・津賀牟礼城などロケ地・モデル地の魅力
岡城跡:竹田藩のシンボルとして描かれる場所
『はぐれ鴉』の中心舞台とも言える岡城(おかじょう)は、実在する山城であり、竹田市の誇る観光地。石垣の高さとスケール感、そして阿蘇山を望む眺望は圧巻で、“荒城の月”のモデルとしても有名です。
作中では、竹田藩の象徴として圧倒的な存在感を放っており、「外から見える竹田の顔」として、民の生活や藩主の威光を象徴する場所として描かれます。

こんな壮大なお城、九州にあったなんて…。赤神先生も“怖いぐらい迫力があった”って言ってたよ。
津賀牟礼城と姫墓伝説:赤神諒の過去作とのつながり
もうひとつ注目したいのが、過去作『戦神』にも登場した津賀牟礼城(つがむれじょう/大分県竹田市)。こちらも竹田市内に実在する山城で、ヒロインの“姫墓”が物語に登場します。
実はこの姫墓、フィクションと思いきや実在したお墓で、赤神諒さん自身が「想像で書いたのに本当にあってびっくりした」11と語っています。
このエピソードは、『はぐれ鴉』における“フィクションと史実の融合”というテーマにも通じるもので、赤神作品の世界観を横断する“竹田小説群”としての奥行きを感じさせます。
\過去作『戦神』はこちら/
小説に登場する“石像・仏像”をめぐる竹田巡礼のススメ
竹田市には、作中に登場する“鳥の石像”“磨崖仏(まがいぶつ)”“だるま”など、実際に見て回れる名所が点在しています。12
たとえば「一ツ眼鳥」の石像は、市内の山中に実在し、観光マップでも紹介されることがある珍スポット。姫だるまの由来となった「姫だるま工房」も観光名所のひとつです。

作中の“姫だるまの由来”は赤神先生の創作だけど、変わった形の“姫だるま”は本当に作られているんだね◎何だかレトロで可愛い…!
また、「上坂田の磨崖仏」や「下木石仏」などは、市内各所にひっそりと佇む“祈りのかたち”。これらを訪ね歩くことで、物語の背景にある“目に見えない信仰と歴史”にふれることができます。

小説で町おこしをしたいと言っていた赤神先生。ドラマも味方に、旅行先に竹田市を選ぶ人が増えそう!“小説の舞台を歩く”って、なんかロマンあるよね◎
まとめ:赤神諒の歴史解釈が光る名作!『はぐれ鴉』が描く“信仰と犠牲の物語”
赤神諒『はぐれ鴉』は、フィクションでありながら、実在の竹田藩(岡藩)やキリスト教弾圧の史実を巧みに織り込んだ“考察型エンタメ小説”です。
表向きは「仇討ちと恋の時代ミステリ」。しかしその内側には、江戸時代の宗教弾圧、隠された信仰、そして「誰にも知られずに社会を支える人々」への眼差しが丁寧に描かれています。

読み終えたあと、きっと「この話は、現代の私たちにも通じる“見えない正義”の物語だった」と思うはず!
≫【はぐれ鴉】原作小説ネタバレ感想📖伏線と結末に涙、復讐と恋が交差するラストを考察
参考資料・出典:
- 岡藩(Wikipedia) ↩︎
- 「荒城の月」ゆかりの観光名所!岡城跡の見どころ(skyticket) ↩︎
- 岡藩の災害史(豊語林) ↩︎
- 赤神諒『はぐれ鴉』刊行記念インタビュー(集英社 文芸ステーション) ↩︎
- 禁教令(Wikipedia) ↩︎
- 宗門改(Wikipedia) ↩︎
- キリシタン洞窟礼拝堂(切支丹洞窟礼拝堂)(たけ旅) ↩︎
- 第3期 中川氏の時代(竹田キリシタン研究室・資料室) ↩︎
- 第3期 中川氏の時代(竹田キリシタン研究室・資料室) ↩︎
- 竹田キリシタン研究室・資料室 ↩︎
- 時代ミステリー小説『はぐれ鴉』舞台となる岡城の魅力とは(城びと) ↩︎
- 磨崖仏を訪ねる(大分市デジタルアーカイブ) ↩︎

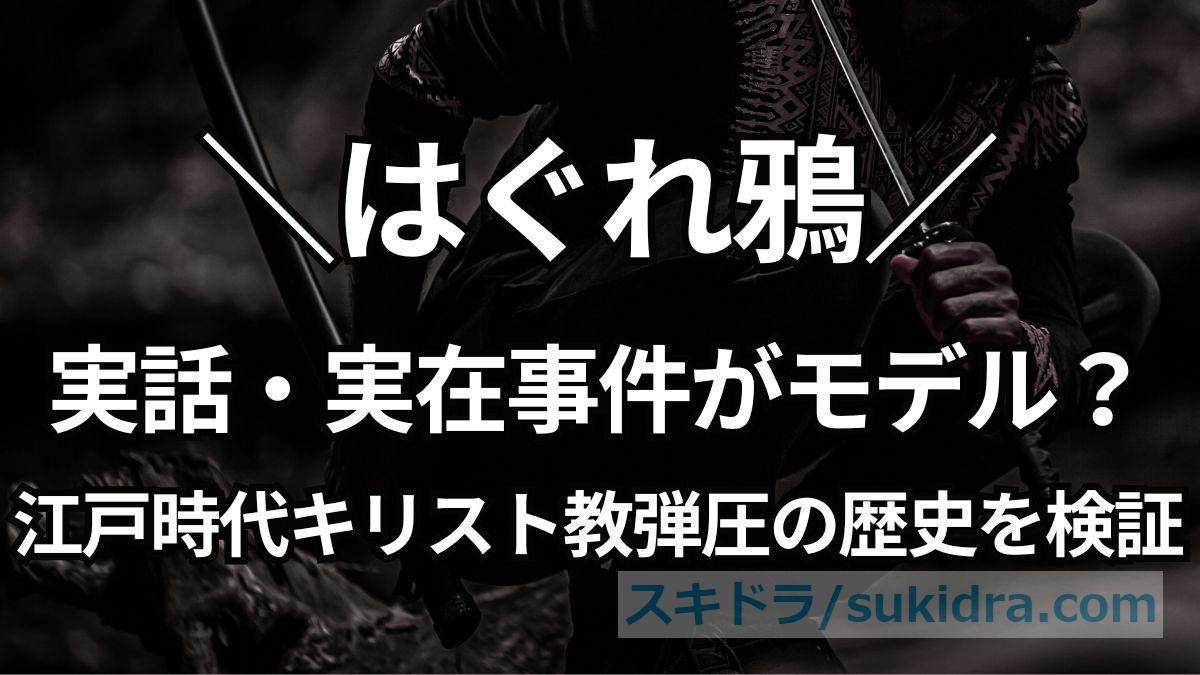


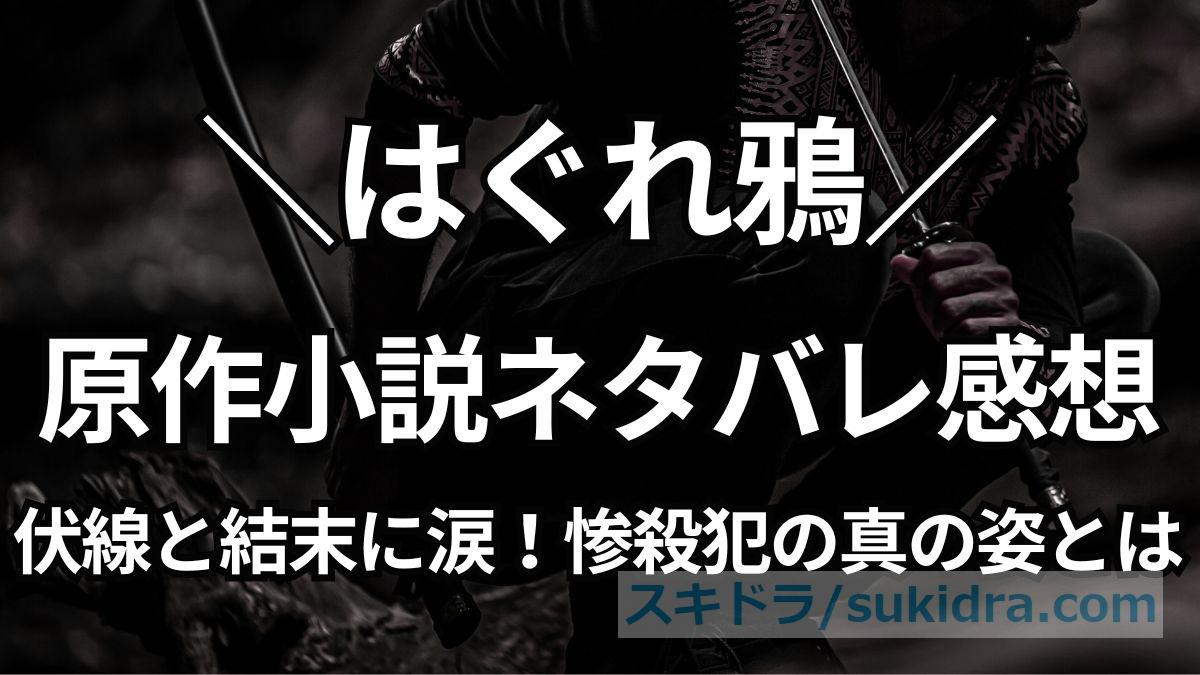
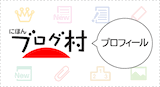

当サイトでは、話題の好きなドラマ情報をお届けします。
原作(小説・漫画・アニメ)のあらすじ・ネタバレ感想、ドラマのあらすじ・ネタバレ感想、原作との違い、原作書籍や配信先を紹介します。
推理小説好きなので、ミステリー要素がある作品が多くなるかも?気になる作品をピックアップしていきます。
他にもタイドラマのサイトを運営しているので、興味のある方は下記のサイトマークから覗いてみてください♡